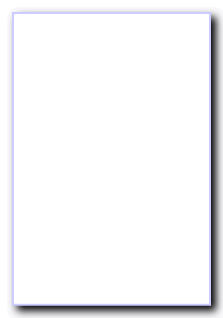
日比谷平左衛門
江戸時代、東裏館に大島屋という旅籠(旅館)がありました。弘化5年(1848年)、その大島屋の主人大島栄蔵に三番目の子どもが生まれました。子の名前は吉次郎、後の日比谷平左衛門です。
子どもの頃、吉次郎は古城町にあった尚古堂という塾に通っていました。この尚古堂こそ村山半牧の父左内が開いたあの寺小屋です。吉次郎は非常に成績が良かったといいます。そんな吉次郎は大島屋に度々宿泊していた江戸の商人松本屋弥助に見込まれて江戸へ丁稚奉公に行くことになります。松本屋に入った吉次郎は弱音も吐かず辛抱強く働きました。そしてそのひたむきな努力が認められ、 吉次郎は番頭に抜擢されたのです。吉次郎17歳の時でした。
慶応年間に入ると不作が続き、開国の影響もあってか大変な不況に見舞われます。全国的に一揆打ち壊しの嵐が吹き荒れたのもこの頃です。松本屋も例外なくその不況のあおりを受け、倒産寸前まで追い込まれてしまいます。主人の弥助は思案の結果、店をたたむことを決意します。奉公人達も悲嘆にくれたそのとき、番頭の吉次郎が「この不況は一時的なもので必ず景気もよくなる、そのためにも今は我慢してがんばれば必ず道は開ける」と進言します。この言葉を聞いた弥助は頭の良い吉次郎ならきっとやりとげるかもしれないと松本屋の命運を全て吉次郎に託すことにしたのです。
全権を任された吉次郎と奉公人達は寝食を惜しんで仕事に没頭しました。その甲斐あって松本屋はなんとか倒産の危機を乗り越えたのでした。
時代が明治に移り、吉次郎30歳の時、浅草にあった日比谷という綿花染糸屋の婿になりました。けれども吉次郎は松本屋に奉公し続けました。そして明治13年、浅草橋にようやく自分の店を持つことができたのでした。
ところが翌年、そのお店が火事のため類焼してしまったのです。しかし吉次郎はこれにもめげず今度は日本橋に店を構えます。けれど日本橋に移ってはみたものの商売は順調には行きませんでした。
行き詰った吉次郎は相場に手を出してしまいます。一攫千金とはいかず、ついに投機に失敗をしてしまうのでした。吉次郎を知る人はその様をあざけ笑います。失意のどん底に落ちた吉次郎は自分の間違いを知り、商いの基本は地道に真面目にやることだと悟ります。
何を言われもいい一からこつこつと商いをやろうと決意します。吉次郎は辛抱強く商いに励んだ結果、店もなんとか持ち直したのでした。そして明治20年、吉次郎40歳のとき日比谷平左衛門を襲名しました。
明治29年、平左衛門49歳のとき、東京瓦斯糸紡績会社を本所に創立し、そこの専務取締役として腕を振るいます。業績は次第に活発化し、とうとう日本の紡績業界を席捲するまでになります。
そんな平左衛門の腕を頼って会社立て直しの依頼が舞い込みました。小名木川綿布。明治21年に設立されたこの会社は最初からなかなかうまく行きませんでした。次第に業績が悪化し倒産寸前まで追い込まれました。何とか再建をと、役員や株主の思案の結果、平左衛門に再建を託すことになったのです。
平左衛門が小名木川綿布に入ると生産管理から手を着け、徹底したムダをはぶき、生産体制の合理化を図ります。やがて利益がでるようになり、たまりにたまった負債も全て償却し、とうとう黒字経営に転換させたのです。小名木川綿布の再建は平左衛門の名を上げます。
次に待っていたのは当時業界大手の富士瓦斯紡績の立て直しでした。人件費の過多と役員の内紛それに旧泰然とした経営に富士瓦斯紡績は破綻寸前でした。平左衛門は自分の片腕で当時鐘紡にいた和田豊治を送り込みます。その和田は平左衛門の期待に応え見事会社を再建させます。
明治45年7月26日の日本新聞に「産業界の一偉観 富士瓦斯紡績 同社が再生復活の親」」の見出しで平左衛門のことが紹介されているのです。
「二十万の錘数、二万の職工、覇を紡績界の一方に称する富士瓦斯紡績会社も僅かに十年の昔を顧みれば、失脚また失脚、逆運また逆運、殆んど解散の悲境に沈淪しつつあった。然もよく此る衰勢を挽回して以て今日の隆盛を見るに至ったのは、実に日比谷平左衛門及び和田豊治両氏が奮闘努力の賜のであって、両氏ありて富士瓦斯紡績会社は初めて今日の盛運を見、両氏莫つせば吾が国の産業界は、実に寒心恐怖すべき経済的大損失を招いたに相違ない。さらば乞う吾人をして、同社に関する研究を公にせしむるに先だち、同社にとっては復活の親たり、日本の産業界に向っては恩人たる日比谷和田両氏に関して少しく紹介の筆を執らしめよ」と。
会社を立て直すことはそう簡単なことではありません。また誰にでもできるものでもありません。犠牲的精神と強い責任感と確固たる使命感がなければ成し遂げることはできないのです。平左衛門が小名木川綿布の再建を引き受けたときの謝礼はほんのわずかだったといいます。また東京瓦斯糸紡績会社では専務という立場でありながら従業員と共に汚れにまみれ作業着で仕事に打ち込みました。
また後に日清紡績を立ち上げるときは、自前の敷地を無償で提供しようとします。こういった損得抜きの真摯な姿勢は人の心を動かすのです。
こうして平左衛門は「破綻整理の名人」とまで言われるようになりました。60歳を超えたときは名実ともに紡績業界の実力者となったのでした。
その後、日清紡績の設立に奔走し、後に会長に就任。また鐘紡の会長にも就任するなど、たくさんの会社の役員を任されます。更に大正7年には支那に日比谷商店を、翌8年には銀行まで建ててしまったのです。
平左衛門は大正9年1月に75歳で亡くなりますが、生誕の地、三条に戻ることはありませんでした。けれども日比谷平左衛門を大きく羽ばたかせた原点は、間違いなく故郷三条にあるのです。