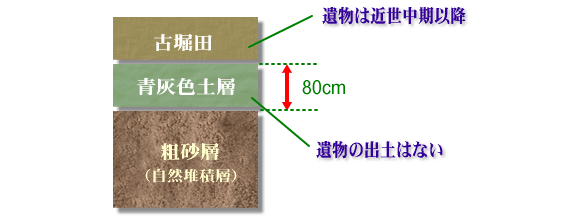
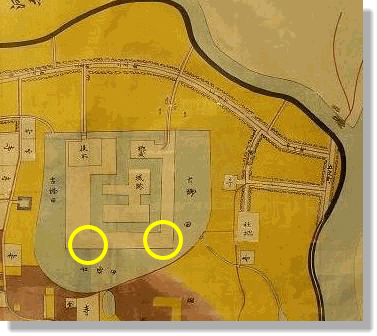
享保裁許書絵図とは?
「享保2年高崎藩領になった一ノ木戸村は町並みを整えて町場を作り商売を始めた。すでに商人の町として、藩のご用金にも応じていた村上藩領の三条町は、自分たちの商売の妨げであるとして、一ノ木戸が農業だけの村に戻るように幕府に訴えた。・・・・村上藩領は黄色、高崎藩領は茶色に・・・描かれている。」
歴史民俗産業資料館資料より
平成10年、西別院の跡地に鍛冶道場が建設されることになり、それに伴い旧古城町周辺の調査が行われました。右写真の黄色い輪に示された場所が発掘調査の対象となりました。調査地は以前西別院の境内があった場所(A)で、ここから西別院の遺構や遺物が出土しました。また数面の整地面や火災面も見られたようです。更に本堂の建替え、整備が行なわれていることが確認されました。遺跡発掘調査によれば遺物は19 世紀から現在に至るまでの陶磁器類や瓦などや室町時代の頃と見られる珠洲焼、青磁の破片、また17 世紀前半から18 世紀頃の肥前磁器などが出土しました。
もう一ヶ所、北三条駅前通りの調査により堀跡が確認されています。当時の調査速報によれば堀跡は享保 3 年頃に描かれた 『 享保裁許書絵図 』 の古堀田に対応すると推定。この古堀田の下層には青灰色土が約80cm 程度堆積し、その下層には粗砂層が相当厚堆積していることが確認されています。粗砂層は自然堆積層と推定され、古堀田跡から出土する遺物は、近世中期以降のもので、青灰色土層中からは遺物は見つからなかったようです。
絵地図から見る近世三条破却後の様子
調査を行なった場所は近世三条城場内の二之丸、内堀部分に該当すると推定されています。現在まで
『享保裁許書絵図』 作成日以前の三条城の状況は分かっていません。平成 7 年に本丸部分にあたるとされている三条小学校のグラウンドの一部が調査されました。その結果、道路状の遺構が確認されています。この道路状遺構は現地表面から lm の深さより確認され、城跡内は、人為的に土地が改良されているものと推測されました。
文政 8 年 に作成された 「古城田畑絵図 」と 「 享保裁許書絵図」と比べますと大部分が埋め立てられ、外堀に近いところは後に水田として、その他は畑地として利用していたと推定されました。調査の結果、実際、水田として残された面が確認されました。西別院が建てられる時、土地が整地され埋め立てられたようです。
出典「遺跡発掘調査速報展(発掘された三条の遺跡)」
三条歴史民俗産業資料館発行図書より抜粋

調査の場所・推定