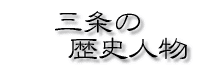諸橋轍次
(もろはしてつじ)漢学者。明治16年(1883年)南蒲原郡森町村(旧下田村)に生まれました。諸橋家は直江兼続の子孫にあたり、庄屋を務めていたと言われています。轍次の父は安平といい、巻梧石に師事し、絵を嗜みました。その後、師匠である巻梧石の二女シヅと結婚し、轍次が生まれます。安平は花鳥画を得意とし多くの作品を遺しました。轍次は大いに勉学に勤しみ、東京高等師範学校を卒業後、師範学校に留まり漢学を教えました。大正8年(1919)に中国に留学した後、漢学の衰退を感じ取った轍次は漢学の振興を図ります。また岩崎小弥太に頼まれて静嘉堂の文庫長として図書の管理を始めます。昭和2年(1927年)になると大修館書店の鈴木一平の依頼で漢和辞典の編纂を始めました。昭和18年(1943年)まず第1巻が完成します。ところが昭和20年2月、東京大空襲の際、全ての資料が燃えてしまうのです。また轍次の視力も相当悪化していたのでした。終戦後、かろうじて残っていた資料をもとに再び編纂の仕事に取りかかりました。多くの人々の労力を得て、ようやく苦節32年を経た、昭和35年(1960年)、大漢和辞典全13巻がついに完成したのです。この功績により昭和40年(1965年)文化勲章受章をしました。その後、都留文科大学学長にも就任しています。昭和57年12月8日、99歳で亡くなりました。
WEB 諸橋轍次記念館
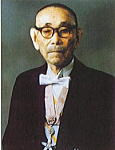

諸橋轍次記念館