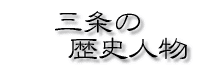◆栗原信秀
刀鍛冶師。文化12年(1815年)旧西蒲原郡月潟村(現新潟市)に生まれました。
父が亡くなった後、母が再婚したため、その嫁ぎ先の三条四ノ町の今井家で育ちました。 信秀16歳の時、京都に鍛冶修業へ。 嘉永元年には江戸へ出て名匠山崎清麿に弟子入りします。その4年後に独立。安政2年京都に上り、「筑前守」に任官し禁裏守護の御番鍛冶の役職に就きます。
そして明治5年には天皇に佩刀を献上し、翌々年には靖国神社の御鏡を打ち上げました。また三条八幡宮や弥彦神社の御神鏡なども制作しました。こうして信秀は輝かしい功績を残しましたが、明治13年(1880年)6月、生誕地三条で66歳の生涯を終えました。
◆外山丈芭
俳人。天保4年(1833年)本成寺村の金子新田の庄屋外山得四郎の次男として生まれました。
丈芭(じょうは)は号で本名は孫郎。丈芭は幼い頃から祖父紹堂より学問や俳諧を習いました。 特に俳句については優れた才能があったと言われています。成人後、金子新田から井栗村の分家池之端領の当主になり庄屋職を継ぎました。廃藩後も井栗の戸長、村長を30年間勤め、村の発展に尽くしました。
明治29年、丈芭は三条・古城町に住まいを移します。その住居を「聴雨巷(ちょううこう)」と名づけ俳諧に没頭していきます。 (聴雨巷の名称は丈芭の別号)
それから後、丈芭は祖翁松尾芭蕉の足跡を慕い、各地を行脚し、数多くの句を残しました。 明治35年には丈芭を称えて、金子新田にある金子神社境内に丈芭翁寿碑が建てられました。明治42年、丈芭78歳の時、白内障を患い、翌年には両眼失明してしまいます。けれども創作活動は衰えることはありませんでした。
大正4年には秋即位大礼の時天盃を拝載しました。そして翌大正5年8月、丈芭は85年の生涯を閉じたのです。
昭和10年三条刀剣会により建てられました。 碑には「刀匠栗原筑前守謙司信秀之碑 陸軍大将鈴木荘六書」と刻まれています。碑は三条市八幡宮の境内にあります。