城が取り壊されるまでをもう少し詳しく見てみましょう。
市橋長勝は弘治3年(1557)美濃国に生まれました。信長、秀吉、家康に仕えます。慶長15年(1610)に伯耆国矢橋藩2万3000石を拝領。大阪夏の陣の功績により、元和2年(1616)越後三条藩へ4万1300石の加増移封となります。:そしてその4年後元和6年(1620)長勝は亡くなります。享年64歳でした。
長勝には嗣子がありませんでした。このため養子の長政が後を継ぎますが、養子という理由で、所領は2万石に減らされ、同年のうちに長政は三条から仁正寺藩に移封されてしまうのです。その後越後藤井藩より稲垣重綱が移封してきますが、元和9年(1623)重綱は大坂城番となって転出してしまいます。
転出後はしばらく出雲崎代官所が支配しました。そして寛永19年(1642)9月9日長岡藩牧野忠成により三条城は完全に取り壊されてしまいます。この9月9日って何の日か知っていますか? 実はこの日は重陽の節句なんです。五節句の一つです。五節句とは、江戸時代に定められた5つの式日をいいます。1月7日の人日の節句、3月3日の桃の節句、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕節句、そして9月9日の重陽の節句を言います。昔から、奇数は縁起の良い陽数と考えられていました。、そして奇数が連なる日をお祝いしたのが五節句の始まりなんです。そのおめでたい日に城を壊されたとして、なんと三条の人々は「面白くない。もう重陽の節句なんてやるものか」と、この日以後、三条では重陽の節句は行なわれていないのです。その後、慶安2年(1649)出雲崎代官所の支配を離れ村上藩の領地となるのです。
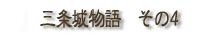
元和年間に造られた三条城はいったいどのあたりにあったのでしょうか。
三条市立図書館に「享保3年裁許絵図」が残されています。(「三条市史」の巻頭にもこの絵図の写しが載っています)この絵図は享保3年(西暦1718年)に描かれたもので、三条町と一ノ木戸村との町場争いのときに、証拠として町が幕府に提出したものだそうです。
この絵図をよく見ると城の中心に「城跡」と書いてあるのが読み取れます。ということはこの時は既にお城が廃城となっていたことがわかります。実は寛永19年(西暦1642年)幕府は長岡藩の牧野家に三条城の破却の命令を出しているのです。そしてさらに歴史をさかのぼると寛永9年(西暦1631年)に三条城が廃城となっているのです。つまり市橋長勝が新城を作り始めてからわずか15年で城が廃城となってしまったのです。
さてこの残された絵図と航空写真を使って、現在、お城がどのあたりにあったのか見てみましょう。マウスのポインターを写真の上に動かして見てください。昔の城の図面に切り替わります。見比べてください。城の輪郭が見えてきませんか。
