ここはフランス衛兵隊兵舎。
アランとフランソワは見回りの途中、兵舎に忍び込んでいた怪しい人間を捕まえ、オスカルの元へ詳細を報告に行った。
「隊長、司令官室を覗き込んでいたので、身柄を確保しました。スパイに違いありません」
「何、司令官室を・・・。何が目的なのか。それで素直にしゃべったのか?」
「いいえ、頑として何もしゃべりません。」
「そうか、では私が尋問しよう。ここへ連行するように。」
「はい、隊長。」
アランとフランソワが二人の女性を連れて入ってきた。
「怪しいって、この二人か? うら若き女性ではないか。」
「はい、隊長。でも、司令官室を覗き込んでいるなんて、何か良からぬことを企んでいるに違いありません。」
オスカルは極上の笑みを浮かべると二人の女性に向かって優しく話しかけた。
「お嬢さん方、お名前を教えて頂けますか?」
「はい、私はレオと申します。」
「私は、デージーです。」
「ほう、レオさんとデージーさん。素敵なお名前ですね。」
二人は真直に見るオスカルの美しさに呆然とし、震える声で素直に答えていた。
「それで、なぜ司令官室を覗いていたのですか? 教えて頂ければすぐに開放いたします。」
「いいえ、それは申し上げられません。絶対に・・・」
「私も、絶対にお話しできません。何があろうと絶対に!」
二人は硬く唇を引き結んだ。
「そうですか、それは残念です。そうするとお二人の身体に聞いてみなくてはなりません。私としてもそんなマネはしたくはありません。ぜひ、お話しください。」
オスカルは脅したりすかしたりしたが、二人は何もしゃべろうとしなかった。
オスカルは、仕方なく決心した。
「では、レオさん。こちらへおいでください。」
「隊長、止めてください! 女性を拷問する気ですか?」
アランの声にオスカルは、冷たい笑みを浮かべただけだった。
オスカルは、彼女だけを隣の部屋へ連れて行き、ドアを閉めた。
残されたデージーは、これから自分たちに何が起こるのか不安で一杯だった。
しばらくすると扉の向こうで、レオの悲鳴があがった。
「止めて、それだけは許して! お願い」
デージーの顔から血の気が引いた。
オスカルが隣室からのドアを開けて姿を見せ、椅子に座ったまま震えているデージーに向かって言った。
「いやあ、彼女も強情でね。まだ話して頂けないのですよ。あなたはお話しして頂けますよね。」
「いいえ、私も決してお話ししません。」
彼女は青ざめ、震えてはいたが、毅然として答えた。
「そうですか、ではこれを・・・。あなたに耐えられますか?」
「止めて、どうして・・・。それはいや、お願い。」
オスカルは、ナインキャットテールと呼ばれる鞭をデージーに見せつけるように握り締めた。デージーはただそれを青ざめながら見つめ、観念したように目を閉じた。
「さあ、早く言ってください。私もこんな手荒なことはしたくはありません。如何です?」
「いいえ、何があろうとも決して・・・。」
デージーは静かに首を横に振ると、背筋を伸ばし真正面を見据えた。オスカルは彼女の覚悟の程を見て取ると、ため息と共に鞭を置き、アランに向かって言った。
「向こうの部屋の彼女もこちらへ連れてきてくれ。」
「はい、隊長」
オスカルは黙って窓から外を眺めていたが、ゆっくりと振り返ると二人に向かって優しく言った。
「お二人とも同じですね。何があろうともお話しして頂けそうもない・・・。なぜですか?」
オスカルの真剣で心配そうな問い掛けにレオもデージーもつい絆されそうになったが、二人は顔を見合わせ、改めて何かを確認するように頷きあった。
オスカルは自分の手に負えないと思った。彼女たちの決意に勝てるような拷問など自分にはできそうも無い。ここはやっぱりあいつに頼もう。
オスカルはフランソワに耳打ちし、彼は司令官室を後にした。
ドアをノックし、紺の軍服を着た一人の男が司令官室に入ってきた。
「オスカル、何の用だ?」
「ああ、レジー。すまない、このお二人なのだが司令官室を覗き込んでいた廉で、アラン達が連れてきたのだが、どうしても理由を話して頂けないのだよ。私は拷問に関しては専門外だし、彼女たちを傷つけたくないし。ここはお前に頼もうかなと思って。」
「なるほどね。それは懸命だ。でも、人聞きが悪いな、そんな言い方だと私がまるで拷問のプロのようではないか。」
「違うのか?」
オスカルはレジーが女性に対して暴力を振るう筈がないと解っていたので、安心して見ていた。
レジーは、レオとデージーを見つめ、それからにっこりと微笑んだ。
「レジーヌ・フランセット・ド・フォーレと申します。どうぞお見知りおきを。」
レジーは二人に礼を取ると優雅にその手に口づけた。そして、上目遣いで彼女たちの反応を見る。
二人はオスカルの『私は拷問に関しては専門外』という言葉に怯えていた。
この男性は拷問の専門家なのだろうか? こんなにきれいで優しそうな男性は今まで見たことはないけれど、優しそうな顔は仮面で本当は残虐非道なのではないかしら?
レジーはしばらく黙って二人の視線を追っていた。そして何かに納得したように、手を差し伸べた。
「マダム、お手をどうぞ。」
彼はデージーの手を取ると彼女を立たせ、背中にそっと手を添えて彼女の肩を抱きかかえるように隣室へ連れて行った。すぐに彼だけ戻ると、今度はレオも同じように連れて行った。
「恐れ入りますが、こちらで少しお待ちください。」
レジーは不安そうな二人を椅子に座らせ、そう言い残すと無表情に部屋を出て行った。
「さて、オスカル。二人の弱点は解ったけれど、本当に口を割らせる必要があるのか?」
「え? もう解ったのか。まだ何もしていないではないか。」
「もう充分だ。あの二人は素人だしな。」
「そうか。ひどいことをしないで話してくれるのなら、助かるが。素人ならなぜああまで頑ななのか、その理由も知りたい。」
「解った。やってみよう。但し、彼女たちにとっては酷いことかも知れないが・・・。悪いがお前はこちらにこないでくれ。」
レジーは司令官室の前で待っていたシルビィにあるものを用意するように言うと、二人の待つ部屋に入り、後手で音高く鍵をかけた。
「さて、一口に拷問と言っても、身体を痛めつけることだけが拷問なのではありません。いろいろあるのですよ。私は既にあなた方の身体的弱点も精神的弱点も把握していると思います。ですから、私が手を下す前にお話頂けませんか?」
「いいえ・・・」
レオは気丈な態度を崩さなかった。デージーは、一瞬うろたえたがレオの目を見つめ、その目に励まされたように落ち着きを取り戻した。
そのときドアをノックして、シルビィが静かに部屋に入ってきた。彼女は布に包まれた重そうなものを抱えてきた。レオとデージーにはそれが自分たちを拷問するための道具だと思い、唇をきつく噛み締め恐怖と闘っていた。
「では、準備も出来たようですから、始めましょう。私がお二人に直接触れる訳には行きませんので、彼女に頼みます。」
レジーはシルビィの耳元に小声で言った。
「レジーさま。はい・・・え? そんな・・・解りました、やってみます。」
シルビィはデージーに近づくと、頭から何かを被せた。そして、レオの背後に近づくと・・・。
二人の声にならない悲鳴が上がった――。
「レジーさま、本当にこれでよろしいのですか?」
レオの肩をマッサージしながら、シルビィが不思議そうに聞いた。
「ああ、お疲れのようだから、徹底的にマッサージして差し上げろ。そうだな、背中もこっていらっしゃるようだぞ。」
その言葉に唇を噛み締め必死で耐えていたレオの身体がぴくっと反応した。
(背中・・・? 止めて〜!)
レオの腕には鳥肌が立ってきていた。
「如何ですか? まだ耐えられますか?」
「ぜ、全然平気です・・・」
とても平気そうには見えなかったが、レオは涙を浮かべながら耐えていた。
一方デージーは、首にケープのようなものを巻かれ、そのくすぐったさに黙って我慢していたが、レオの惨状を見て怯えていた。
(私もあれをやられたら、耐えられないわ。ど、どうしよう。)
「シルビィ、こちらのご婦人にも頼む。」
「はい、レジーさま。」
「こちらは、そうだな・・・その細く長い首を優しく揉んで貰おうかな。」
(ど、どうして、私の一番弱い場所が解ったの。止めて〜)
シルビィの手がデージーの首筋に触れた瞬間、総毛立った。
(ひえ〜〜〜っ!!)
数十分後――。
レジーは考え込んでいた。
通常素人ならこの辺でギブアップの筈。それなのに二人はまだ一言もしゃべらない。
これならこの道のプロにもなれる根性だ。
なぜ? この二人は何を守ろうとしているのか?
仕方がない、奥の手を出すか。この手は自分としても使いたくなかったのだが。
「シルビィ、あれを」
「はい。」
シルビィは、先ほど持ってきた包みを開いた。
二人は思いもかけぬものが出てきたので、びっくりしていた。
(なぜ?)
(それをどうするつもりなの?)
二人はレジーがそれを使って何をするつもりなのか、皆目検討がつかなかった。
レジーは、それを手に取ると二人に向かって言った。
「これが何だかもちろんお解りですね。」
「知りません・・・」
レオは顔色を変えたが、必死で首を振った。
「ご存じない。おかしいですね。では、これがどうなってもいい訳ですね。」
デージーは自分の目の前で起こっていることが信じられなかった。
(そんなばかな。なぜ? どうしてあれがここに・・・)
レジーは箱を開けると中身を取り出し、そこにあったテーブルの上に並べた。
「関係ない人間にはこれがどうなろうとどうでもいいことでしょう。でも、あなた方二人にとってこれは命の次に大事なものなのではないですか。」
レジーはそのうちの1つを手に取ると、レオの目の前にかざした。
「そ、それがどうだというのですか?」
レオは精一杯平静を装って尋ねた。
「いや、これをこうしたらどうかと思いましてね。」
レジーは手の内のそれをテーブルに戻すと、たまたまそこに置いてあったアジビラをつかみ盛大な音を立てて引き裂いた。
「それとも、暖炉に薪の替わりにくべてしまいましょうか。勢い良く燃えるでしょうね。
こんな風に。」
レジーは二つに裂いたアジビラを暖炉に放り込んだ。
それは瞬く間に炎に呑まれ、薄っぺらな残骸となった。
レオとデージーはテーブルに置かれた物が同じ運命を辿ることを想像しただけで、顔面蒼白となり、身体が震えた。そして、観念したように項垂れた。
「止めてください。それだけは、お願いです・・・。」
「では、答えて頂けますね。」
二人は顔を見合わせると苦悩の表情を浮かべた。
「でも、どうしても、言えないのです。どうしても。言ってしまったら、私たちは・・・」
二人の目から溢れそうな涙を見て、レジーは考えを改めた。
(どうもそう単純な問題ではないらしい。これ以外に二人の弱点として考えられるの
は・・・)
二人に涙を拭くハンケチを渡すと、レジーはさり気なく聞いた。
「失礼ですが、お子さんは、何人ですか?」
「え、子供? ふ、二人です。」
「私も、二人です。」
淡々と答えたように見えた二人だったが、激しい動揺がレジーには感じられた。
「では、今お子さんはどちらへ?」
レジーのその問いに二人の目からは涙が堰を切ったように溢れ出し、声を上げて泣き出してしまった。
レジーは二人が落ち着くのを待って、真摯な態度で話し掛けた。
「私はオスカルの古くからの友人で、あなたたちの味方です。私を信用して話して頂けませんか? 決して悪いようにはしません。必ずお力になれる筈です。」
二人は涙に潤んだ瞳を彼に向けると、こっくりと肯いた。
「実は・・・」
二人から話を聞いたレジーは、オスカルに後を頼むとシルビィとエミーを連れて、どこかへ出掛けて行った。
しばらくして、レジーは一人の女をオスカルの前に連れてきた。
「レジー、そちらは?」
「あの悪名高きサロン『ANTARES』のソレイユだ。」
「なんだって、悪の権化と言われるソレイユか。ふん、さすがに不敵な面構えだな。それで、あの二人は手下なのか?」
「いいや、違う。あの二人は子供を人質に取られて、脅されていただけだ。」
「何だって、子供を人質に・・・。だから、あんなに口が堅かった訳か。それで子供はどうした?」
「もちろん、無事だ。助け出して、今エミーとシルビィが家まで送って行っている。」
「ここへ連れてくれば良かっただろうに、母親がいるのだから。」
「いや、それが・・・。子供には内緒にしておきたい部分もあるのかなと思って。」
「?」
オスカルは彼が何のことを言っているのか解らずに、不思議な顔をしていた。
「アラン、こいつは営倉にでも放り込んで置け。後で取り調べるから。」
ソレイユは、オスカルに食い入るような視線を向けたまま、アランとフランソワに引きずられるように連れて行かれた。
「では、二人を安心させてやろうか。」
レジーは、隣室の二人に子供たちの無事を伝えた。
「あ、ありがとうございました。」
二人は手を取り合って喜んでいた。
「今度は、あんな手合いに付けこまれないように気をつけてくださいね。かわいいお子さんたちのためにも。」
「はい、今後はこんなことのないように気をつけます。」
「子供たちから絶対に目を離さないようにします。」
デージーとレオは、真剣な眼差しで答えた。
レジーはその返答ににっこりと微笑むと声を潜めて言った。
「ただし、それは個人でこっそりと楽しむだけにしてください。ソレイユはもう捕まえたから心配はいりませんが、また衛兵隊の隊員やオスカルに見つかると今度は庇いきれないかも知れません。」
「はい、すみませんでした。」
「もう、決してしません。」
二人は頬を赤らめると消え入りそうな声で言った。
「お子さんがお待ちでしょうから、お帰りになって結構ですよ。」
「あ、レジー。そんな勝手に・・・。」
レジーはオスカルを遮ると二人のためにドアを開けた。二人は顔を見合わせると、名残惜しそうにオスカルを振り返り振り返り司令官室から出て行った。
司令官室でレジーと二人きりになったオスカルは、彼を問い質した。
「レジー、どういうことなのか、説明して貰おうか。」
「ん〜、そうだなあ。あの二人の名誉の為に言えないな。」
「名誉? そんな大げさな。」
「子供は無事だし、悪いやつは捕まえたし、何も問題はないだろう?」
「でも、・・・」
「じゃあ、俺は仕事があるから行くぞ。またな。」
レジーは、隣室から先ほど使った例の包みを大事そうに抱えるとそそくさと部屋を出て行った。
「あ、そうだ。レジー、それは一体何だったのだ? あの二人はそれで話したのだろう?」
その問いが聞こえたのか聞こえなかったのか、レジーは何も答えずにドアを閉めた。
結局、司令官室に釈然としないままのオスカルが一人残された。
あー、危なかった。これをオスカルに見られたら大変だ。
これの威力は絶大だったな。
ま、当然だな。俺の秘密の宝物なんだから。
良かった、あの二人が早々に折れてくれて。
破るなんてとても俺にはできないからな。
買うときも苦労したのだ。
「プレゼントにしますので、包んでリボンをお願いします」って、いやちょっとわざとら
しかったかな。
レジーが包みの中からそっと取り出したもの、それは『ベルサイユのばら』完全復刻版セットだった。
「ねえ、レオさん。うまく撮れた?」
「もちろんよ。デージーさん、あなたは。」
「当然よ。アップで撮れたわ。ほら、見て?」
二人がソレイユに脅されて司令官室を覗き込んでいた理由がそこにあった。
二人の手にあるもの、カメラ付き携帯電話。その中には様々な表情のオスカルが写っていた。
「よかったわね、このデータを消されないで。」
「彼はこのデータには気がつかなかったのよ。」
「彼があの本を出したときはどうしようかと思ったけど、良かったわ破られなくて。でも、あの本は誰の物なのかしら?」
「まさか、彼のではないわよね。」
「まさか、ね。」
「やっぱり、オスカルさまは素敵ね〜♪」
「凛々しくて、美しいわね〜(はあと)今日は幸せだったわあ。」
二人は興奮冷めやらず、足取りも軽く帰途についた。
その頃レジーは、パソコンでアルバム作りに勤しんでいた。
「おっ、このオスカルの表情はいいなあ。さすが女性ファン。目の付け所がいい。この点はソレイユに感謝しなくてはな。二人が携帯で撮ったオスカルの写真をメールでソレイユに送らされていたのだから。それをちょっと俺が失敬したなんてことがオスカルにばれたら・・・。」
―おしまい―

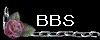
2003.08.29


