王党派として最後まで諦めず孤軍奮闘してきたジャルジェ将軍ではあったが、国王に続き王妃も処刑され、自分の生きる意味さえ見失っていた。
本人は今更命も惜しくもないし、財産などにも固執していたわけではなかったので、国外に逃亡する気など更々無かった。しかし、このフランスの地に生きる希望を見出せなくなってしまい、余生を外国で静かに暮らしたいとの妻のたっての希望で、やっと出国する気になり、最後に亡き娘の想い出の地であるアラスにやって来たのだった。
この地の領主として領民に対して常に誠実な態度を取っていたジャルジェ家だったので、このアラスの別荘もそれほど荒らされる事なく、外見上はなんとか以前のままの姿を保っていた。
しかし、金目の物はさすがに持ち出されてしまったらしい。
二人の結婚式以来、アラスの別荘には足を踏み入れたことはなかった。娘を失ったあの日、ここに二人の亡骸が運ばれたのは知っていたが、自分の立場上来ることはできなかった。残酷ではあったが、それを妻にも厳命し、葬式に出ることを許さなかった。だから、二人は最愛の娘の死に顔は見ていない。自分たちが覚えているのは、結婚式でのオスカルの輝くような笑顔だけだった。
ベルサイユからアラスまでの道すがら、レニエ・ド・ジャルジェは最愛の末娘へ告げることの出来なかった想いを反芻していた。
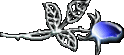
オスカル。
私がお前を普通の娘として育てていたら、お前をこんなに早く失うことはなかったのだろう。
お前が生まれた、あの日。
なぜ、お前を男として育てるなどと考えてしまったのだろう。
私は息子が欲しかった。これだけは嘘偽りのない本当の気持ちだった。
お前の上に既に5人の女の子が生まれていた。
こんどこそ、男の子が欲しかった。
ジャルジェ家は代々軍隊を指揮する家系だ。
女の子がいやな訳ではない。
ただ、一人だけでいい、私の跡を継ぐ男の子が欲しかったのだ。
お前の母は、5人目の子供を産んだとき、これ以上子供を産んだら命の保証はできないと医者に宣告されていた。けれど、私のために6人目の子供、つまりオスカルお前を命がけで生んでくれた。
知ってのとおり私は貴族社会には珍しく愛人というものを持たず、一途に妻を愛している堅物で変人だと言われている。だから、妻以外の女性と子供を儲けるなど考えることも出来なかったのだ。本当は、お前の母はそれを不本意ながら望んでいた。自分が男の子を産むことが出来なかったことへの罪滅ぼしのつもりなのだろう。もちろん、私は断わった。
だが、その頃存命だった両親がお前の代でジャルジェ家をつぶすつもりなのかと大層怒り、愛人候補を山ほど連れてきたのも事実だ。結局私はいくら言われても、愛人は持たなかった。だから、オスカルお前が私の最後の子供だったのだ。
あの日、お前の元気な産声を聞いたとき、神の声を聞いたような気がした。いくら止めても生むと言って聞かなかったお前の母の強さを持った子供、お前をひと目見たときに感じた不思議な感覚。この子は普通の人生を送ることはないだろうと漠然と感じたのだ。そのときに私は決心してしまった、お前を男として育てようと・・・・・・。
その結果、私はこんなに早くお前を失うことになった。
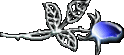
別荘の裏手にある小高い丘の上。
二人はここに来ることを望んでいた筈だった。
でも、実際に並んだ二つの墓碑を見て、しばらく立ち竦んでしまった。
「オスカル、アンドレ・・・。遅くなってしまって、ごめんなさいね。」
母は、二人の墓碑に花を手向け、静かに祈りを捧げた。そして、耐え切れずに泣き伏した。
父は、妻の肩をしっかりと抱き寄せ、ただ風に吹かれ墓碑を見つめていた。
「オスカル。私はお前の行動を怒ってはいない。ただ私が言いたかったのは、お前が親不孝者だということだ。親より先に死ぬなどと、これ以上の親不孝があるだろうか。どうして、死んだ。どうして・・・。」
父は決して泣くまいと、唇を噛み締めていた。
泣き続ける妻を抱きかかえ、父は少しでも休ませようと別荘の扉を開けた。二人は、何もなくなってしまった筈のピロティに入った。
開けた扉から一筋の光が差し込み、ある一角を照らした。
二人はそこに素晴らしい夢を見た。
あまりに神々しく、あまりに清いその姿は何人も触ることさえできず、そこに掛けられたときのままに存在し、柔らかな笑顔で二人を迎えてくれた。
二人の目からは、幸せの涙が止め処なく零れ落ちた。
ここで二人を待っていてくれたのは、まぎれもない我が娘。
これ以上の笑顔はない程幸せに満ち溢れた我が娘の姿。
あの娘は幸せだったのだ。
短い日々ではあったけれど、アンドレと二人で・・・。
娘の肖像画を例え眼を瞑っても見えるほど心に充分に焼き付け、静かに別れを告げると、二人は本当に幸せな気分で別荘の外に出た。そして、二人は何かを感じて別荘のバルコニーを振り返った。そこに確かに見えたのだ、アンドレに肩を抱かれ、幸せそうに微笑みながらこちらに手を振っているオスカルの姿が。
父上、母上、ありがとうございました。
どうぞいつまでもお元気で・・・。
温かいものが二人をやさしく包み、二人は満足して馬車に乗り込んだ。
「あなた、あの子はここで幸せに暮らしているのですね。」
「そうだ。ずっとアンドレと二人でここに。」
「ここに来て良かったですわ。」
母は、やっと肩の荷が下りたように微笑んだ。
父は、本当に久しぶりに穏やかな笑顔を妻に向けた。
ありがとう、娘よ。
私の自慢すべき娘よ。
いつかまた会えるそのときまで・・・
さようなら

