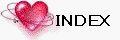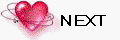「レジー、アメリカから戻ったばかりで悪いが、『ブルーシャーク』をまたご指名だ。」
レジーの直属の上司で、表向きはフランス海軍歩兵隊少将、実際は諜報員達の司令塔、アルベール・ガストン・ド・ラップは少し気難しい顔で、レジーに告げた。
「了解。貧乏暇なしですね。」
レジーはラップ少将の前に立ち、窓から差しこむ日差しに目を細めて、苦笑しながら彼の顔を眺めた。思えば彼の勧めで危険極まりないこの世界に足を踏み入れた。彼はレジーの諜報員としての素質を逸早く見抜き、フランスのためにレジーをこの世界に誘った。レジーより10歳程年上で、短く刈り揃えた栗色の髪と茶色の瞳を持つ穏やかな性格の上司は、信頼と尊敬に値する人物だった。
レジーと呼ばれた男、レジーヌ・フランセット・ド・フォーレは訳ありで女の名前を持っている。表向きはフランス海軍歩兵隊中佐だが、実際は『ブルーシャーク』というコードネームを持つフランス№1の諜報員だ。
完璧なヴィジュアル系で蜂蜜色のくせのないストレートの長い髪にすみれ色の瞳を持ち、時々2枚目半にもなる優しく陽気な性格で、女性には大いにもてた。典型的なフェミニストで、“来る者は拒まず、去る者は追わず”を文字通り実践している男だったので、女性に恨まれることもなかった。しかし、諜報員としては在る意味失格で、女性に対しては絶対に暴力を振るえず、敵側の女性諜報員に攻撃を受けた場合でも、防御一方で攻撃することが出来ず、今まで何度も命を落としかけていた。彼にとって自分では気が付いていないが女性は鬼門だった。『ブルーシャーク』の唯一の弱点、それは『女性』だった。
例えその女性が美しくなくても、若くなくても、性格が悪くても、彼は女性に弱い。世間の男並に若い美人だけに弱い訳ではない所が彼の彼たる所以である。
「レジー、次の仕事は腕の立つ女性がどうしても必要だ。」
「女性ですか、なぜ?」
「お前と夫婦役で潜入して貰いたいのだ。誰か心当たりはないか?」
「心当たりですか、ありませんね。どうせ危険な仕事でしょう。ご存知の通り私はフェミニストですからね。女性を危険な目に合わすのは自分の主義に反します。」
「解った、多分そう言うだろうと思っていた。では、こちらで探そう。私もお前が女性と組むのは賛成しない、女性の為に命を捨てようと手薬煉引いて待っているようなところがあるからな。おかげで『ブルーシャーク』は女に弱すぎると評判だぞ。」
「そうですか、それはなかなか嬉しい評判ですね。」
レジーは愉快そうに笑った。
「確かに女性を危険な目に合わすのは私だって好みはしない。しかし、これは国王陛下のご命令なのだ。」
二人は真剣な表情で黙って顔を見合わせた。
レジーはオスカル・フランソワ・ド・ジャルジェのことを思い出していた。彼の幼年仕官学校の同級生で、女でありながら、父ジャルジェ将軍の跡を継ぐために男として育てられ、現在フランス近衛隊の連隊長を勤めている。この前の任務で久しぶりに彼女に会えたのだった。
この仕事にはオスカルを巻き込みたくない。俺がお前の名前を出さなくても、絶対にお前の名前が挙がってくるだろう。軍隊にいる腕の立つ女なんて、フランス中捜したって、オスカルお前しかいないからな。そしてお前は断ることはできないのだろう。オスカル、お前には会いたい。でも、俺はお前を危険な目には合わせたくないのだ。お前がこの仕事を受けるなら、俺は・・・・・・。
オスカルは父、ジャルジェ将軍より呼び出されて、父の執務室へ向かっていた。
「ジャルジェ准将です。」ドアをノックして、声をかける。
「入れ。」
「失礼します。」
ジャルジェ将軍は、娘オスカルの顔を見ると、少し顔を曇らせた。自分の立場上、部下でもある娘に命令しなくてはならない。どんなに危険な仕事であろうと、国王陛下のご命令なのだ。将軍は心を決めるとオスカルに話し始めた。
「オスカル、これから私が言うことを良く聞いてくれ。お前にある任務が来た。これは男では出来ない仕事で、国家諜報機関からお前を名指しできたものなのだ。もちろん危険な仕事だと思う。詳しい事情は私にも解らない。但し、軍務に就いている者として、断ることは出来ない。断るなら軍隊を辞めるしかないだろう。」
「諜報機関と言うと、レジーからですか?」
「いや、彼ではなく、彼の上層部からだ。彼はお前の名前は出さなかったらしい。」
「諜報機関の仕事と言うと、どんなことをするのかまったく解らない訳ですね。」
「そうだ。父親としては、お前をそんな任務に出したくはないが。これは国王陛下のご命令なのだ。どんなことがあっても、お断りする訳にはいかない。」
「父上、ご心配いりません。私を名指しで来た仕事です。私とて軍人の端くれ、もちろん、お受け致します。」
「オスカル・・・。」
「それで、いつからその任務に就けばよろしいのですか?」
「それが、今すぐなのだ・・・。」
「えっ、今すぐですか?」
「もう、迎えの馬車が来ているのだ。身一つで来て欲しいと・・・。事情が事情なので、アンドレも付いて行けない。お前一人で行かなくてはならない。お前が一体どこへ行くのか、それさえも私には解らない。いつまで掛かるのか、いつ帰ってこられるのか、何も解らないのだ。ただ、どこかでお前を待っている諜報機関の人間の指示に従うようにと・・・。」
「解りました。父上、行ってまいります。母上とばあやをよろしくお願いします。」
オスカルは父に向かって背筋を伸ばし敬礼すると、静かに部屋を後にした。
「オスカル・・・。無事に帰ってこい。」
父は少しも臆せず出立した娘を誇りに思いながら
、敬礼を返した。
オスカルが迎えに来ていた馬車に乗ると、御者は黙って馬を走らせた。オスカルは結局、誰にも一言も告げずに出発した。どうせ行き先も目的も自分にさえ解らないのだから・・・。
しばらく走ると御者は馬車を止めて、オスカルに話しかけた。
「ジャルジェ准将、これより先は行き先を知られては困りますので、馬車の窓を閉めさせて頂きます。何も見えませんがお許し下さい。」
「解った。」
御者が、馬車の窓に付いている覆いを外側から完全に閉めたため、外の様子を窺い知ることは全く出来なくなった。オスカルはこれで自分がどの方向に向かっているのかさえ、解らなくなった。
オスカルは自分のこれからを考えまいとしていたが、やはり不安な気持ちを押さえることは出来なかった。自分はどこに行くのか、そして一体何をするのか、なぜ自分が名指しされたのか。しばらく考えていたが、どうせ考えても事態が好転する訳ではないと腹をくくった。
馬車がやっと止まり、扉が開いたのはもう辺りが夕闇に包まれようとしていた頃だった。ここまでかなりの時間を要したが、回り道をしたのかも知れないし、ベルサイユから真っ直ぐここへ向かったのかも解らない為、ここがベルサイユからどの程度離れているのかも、伺い知ることは出来なかった。オスカルは馬車から降りると身体を伸ばし、辺りを見回した。そこは森の中の古城で、御者はオスカルに入り口を示唆すると黙って帰っていった。オスカルは躊躇せず示唆された入り口から入って行った。明かりが灯され、扉が開け放たれたままになっていた部屋に入っていくと、入り口に背を向けて椅子に座っている人間が見えた。
「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ参りました。」
オスカルが敬礼し、声を掛けると、椅子に座っていた男は立ち上がり、豪奢な金の髪を揺らして振り返った。
「あっ、レジー。お前だったのか。」
「やっぱり来たのか。オスカル。」
どこか残念そうなレジーの声だった。
一瞬緊張していたオスカルの顔に穏やかな表情が浮かんだが、次のレジーの冷たい言葉と態度にあっという間に凍りついた。
「オスカル、俺の仕事は知っているな。伊達や酔狂でフランス№1諜報員と言われている訳ではない。俺は今まで女と組んだことは一度もない。命取りになり兼ねないからだ。今回は上層部の決定で俺も断ることは出来なかったし、お前も断ることが出来ないのも解っていたから、仕方がない。女性に手荒なことをするのは俺のポリシーに反するのだが、まず、お前がどの程度の腕なのか自分で解って貰う。かなり痛い思いをさせると思うが、お互い仕事だ、我慢して貰おう。オスカル、剣を抜け、いいか遠慮はいらない、本気で掛かって来い。」
レジーは自分も剣を抜くとオスカルと剣を合わせた。
「本気で?」
「そうだ、こないのならこっちから行くぞ。」
レジーは、オスカルの剣を一瞬で叩き落した。オスカルは余りの速さと手に残る衝撃に何が起こったのか解らなかった。
「あっ、今のはちょっと。もう、一本。」基本姿勢を取り直す。
「何度やっても同じだと思うが・・・。」
また一撃でオスカルの剣は落とされた。まるで勝負にならない、あまりの力強い剣捌きに手が痺れ、呆然としているオスカルを尻目に、
「力の差だ、解るな? お前の剣の技術はいいのだ。ただ、力が足りない。技術の差がなければ、後は力の差で勝負がついてしまう。俺の射撃の腕前は解っているな? お前の射撃の腕はそれなりに認める。但し、相手の眉間を撃ち抜けないような脆弱な精神ではだめだ。この仕事で同情や躊躇は命取りになるからだ。自分の命だけではない、仲間の命も掛かっているのだから、その辺は理解できるな? 後は素手の格闘だ。掛かって来い。これはもともと男と女だからハンディがありすぎるがな。」
男と女の差という言い方にカチンときたオスカルは、向きになってレジーに殴りかかった。彼はその右手を軽く掴むと肩の関節を締め上げた。
「あっつ!」
「もう、降参か、オスカル。」
「誰が・・・。」
レジーがほんの少し締め上げた腕に力を入れる。
「オスカル、強情を張ると腕が折れるぞ。」
「いやだ・・・、降参しない。」
余りの痛みで気が遠くなりながらも、強情を張りつづけた。
「いいか、オスカル。これから任務に就くまでの約1ヶ月ここでお前の訓練を俺が担当する。女としてはもちろんお前も強い。但し、この仕事には命が掛かっているのだ。剣のセンスはいい、射撃もまあまあだ、だが筋力がまだ足らない。それに素手で闘えるだけの技術がない。女の力でも闘える技を身に付けなくてはならない。今お前を押さえているのは、関節技で力は要らない、女性向の技だ。1ヶ月以内でマスターして貰う。俺の考えている基準にまで達しなかったら、この仕事は絶対に受けさせない。危険過ぎるからな。」
レジーはやっと彼女の手を離した。
「レジー」
オスカルは、痛みで痺れた手を擦りながら彼の名を呼んだ。
「ここでは、俺はお前の友達じゃないし、男と女でもない。いいか、甘えるな、返事は!」
「はい、解りました。」
「まず、服を脱いで身体を見せて貰おうか。」
「え?」
「聞こえなかったのか、服を脱げと言ったのだ。全部脱げとは言わない。早くしろ。」
「はい。」
オスカルは言われたとおり、軍服を脱いだ。そしてしばらく躊躇したが黙ってブラウスを脱いだ。
「悪いが、コルセットも邪魔だ、外して貰おう。」
オスカルは唇を噛みしめ、コルセットを外し、胸元を両手で隠した。
「気を付け!」レジーのきつい言葉にオスカルは驚きながらも反射的に気を付けの姿勢を取った。
レジーは、オスカルの腕を持ち上げると自分の言うとおりに動かさせて筋肉の具合を調べ始めた。そして両腕、背中、腹、足等全身の筋肉をつぶさに調べた。
「もう服を着ていいぞ、悪かったな。」
レジーは彼女のブラウスを手に取ると、肩に羽織らせ、背を向けた。
オスカルは自分が惨めで、服を着ながらつい瞳を潤ませた。
「オスカル、泣くな。もし、泣いたらその場で帰すぞ。意地でもついてこい。」
「はい。」
オスカルは自分の置かれた立場が、やっと解ったのだった。頭では解っていたつもりだったレジーの仕事、彼がどれほど厳しい世界を今まで生き抜き、№1と呼ばれるまでになったのか。例え自分が望んでここに来た訳ではないにしろ、オスカルの負けず嫌いの精神がむくむくと頭を擡げてきたのだった。
(覚えていろ、レジー。絶対に負けないからな。)
オスカルの闘争心に火が点いた。
「さて、早速だが明日からのスケジュールだ。目を通しておいてくれ。それからこの城の中には俺とお前しかいない。召使いはいないからな。自分のことは自分でしろよ。」
「あの、このスケジュールだが、ダンスって、これは一体何なのだ。」
「まだ詳しくは教えられないが、お前と俺は貴族の夫婦ということで潜入する予定だ。だから女性パートのダンスの練習もある。その前にドレスに慣れて貰わないと困るがな。」
「ドレスに慣れる? 私がドレスを着るのか?」
「そうだ。女性の役だぞ、当たり前だろうが。そうでなければ、同僚の男で用は足りるのだ。」
「ドレスなんて、ろくに着た事ないぞ。」
「だから困るのだ。俺の方が着慣れているくらいだからな。明日から特訓だぞ。」
「何かとんでもない仕事を引き受けてしまったような気がする。」
「そうだな。覚悟は出来たか?」
オスカルは黙って頷いた。
「そうか、では食事して今日はもう休め。明日から本当にきついからな。2階の一番右側の部屋を使ってくれ、俺はその隣の部屋にいる、何か用があれば言ってこい。必要なものは用意しておいてある筈だ。」
「解った・・・。」
部屋に行ってみると確かに日常生活に必要と思われるものはすべて用意してあると思われた。クローゼットには彼女のための着替えもいろいろと用意されていた。オスカルはそのままバルコニーに出ると外の景色を眺めた。満月だったので、かなり明るく周りが見渡せた。城は鬱蒼と生い茂る木々に囲まれているようで、すぐ眼前に小さな湖が見えた。
いったいここはどこなのだろう?
これから1ヶ月、レジーと二人きりでここで暮らすのか?
あんなに冷たいレジーは今まで一度も見たことがなかった。
いつも陽気でやさしい男だと思っていたのに・・・。
あれが本当の彼の姿なのか?
オスカルは不安で胸が締め付けられるようだった。
絶対に泣かない!
絶対に負けない!
彼女がそう決心したとき、バイオリンのやさしい調べが聴こえてきた。
「レ・・・レジー? 私のために弾いてくれているのか・・・?」
彼女の心を慰めるような穏やかで暖かな音色。
オスカルはその音色に耳を傾け、次第に心を落ち着かせていった。
「あいつはもともと器用な男だと思っていたが、バイオリンもかなりの腕前なのだな。」
彼女はレジーのバイオリンにうっとりと聴き惚れ、そのまま穏やかに眠りについた。バイオリンは夜半までずっと彼女に許しを請うかのように静かに奏でられていた。
―つづく―