画家のアルマンが帰ってからも、オスカルはずっと資料を読み続けていた。
「オスカル、あんまり根を詰めるな。」
アンドレがオスカルの手から資料の束を取り上げる。
「何をする。アンドレ!」
「もう、何時間経ったと思っているのだ。さっきも声を掛けたのだぞ、全然反応しなかったくせに。もう夜だ。続きは明日にしろ!」
「ああ、ごめん。そんなに経っているのか。」
「食事にして、早めに休め。」
「あの、もうちょっと・・・。だめか、アンドレ?」
甘えた声で、上目遣いに彼を見つめる。
「だめ、そんな眼で見ても、だめだ!! まったく人の弱みに付け込んで・・・。」
そこで、上着のポケットにあるものを思い出し、小さな包みを取り出すとそっと彼女に手渡した。
「ああ、そうだ。オスカル、これ・・・。貰ってくれるか?」
「何、私に? 開けていいのか?」
中から出てきたのは、サファイヤを小粒のダイヤモンドで縁取った、プチ・ペンダントだった。
「これは・・・」
「お前にアクセサリーを贈ったことはなかったけれど、似合うかなと思って・・・。
大した物じゃないのだけれど。」
「ありがとう、アンドレ。すごくきれいだ。着けてくれるか?」
彼女の後ろに回り、ペンダントを着けてやった。
「綺麗だ。お前の肌によく似合うよ。お前の瞳の色に似ている色を捜したのだ。」
「ふふ・・・。くすぐったいな・・・。私は、装飾品なんて欲しいと思ったこともなかったのに、こんな・・・。」
涙ぐみ言葉が出てこない。
「どうした、オスカル。」
「幸せ過ぎて・・・。私はやっぱり女なのだな? こんなに嬉しいなんて・・・。自分でも知らなかったぞ・・・。」
彼女の頬を幸福の涙が伝う。
「オスカル・・・」
アンドレはやさしく彼女の涙を拭い、首筋にひとつキスを落とす。そしてその胸にそっと抱きしめた。
「オスカル、食事ここでしようか? 持ってくる。」
「私は、ショコラが飲みたいな。」
「わかった。待っていろ。」
アンドレは部屋を出て行った。
彼女は自分の胸元に光るペンダントを鏡に映し、嬉しそうに見つめていた。
(ふふふ・・・、私はまるで女みたいだな。ふふ・・・。あ・・・れ・・・?)
突如、オスカルの目の前が暗くなった。
立っているという気がしなくなり、雲の上を歩いているように感じられた。
そして、よろめいて側にあった椅子を倒した。
ガターーーン!!
大理石の床に倒れた椅子は反響して、思ったより大きな音を立てた。
その刹那、胸を突き上げられるような衝撃を覚えた。
胸に込み上げて、喉から溢れ出るものをオスカルは抑えきれなかった。
口の中をいっぱいにした生温かい液体を、吐き出さなければならなかった。オスカルは口元に手を当てて、激しく咳き込んだ。
「オスカル、どうした?」
アンドレが椅子の倒れた物音から異変を感じて部屋に飛び込んできた。
おびただしい量の血が、大理石の床に大輪の紅薔薇の花を咲かせていた。
「オスカル!! オスカルーッ!!」
喀血は繰り返されて、その度にオスカルは意識がより薄れるのを感じていた。
自分に向かって必死の形相で走ってくるアンドレの姿が、ストップモーションのようになり、彼の声がだんだんと聞こえなくなる。現実が遠のき、オスカルの意識は完全に途切れていった。
アンドレは、意識を失った彼女を間一髪で抱きとめ、そのままそっと床に横たえた。
「オスカル!! オスカル!!」
アンドレの必死の呼び声にも、彼女はまったく反応しない。
彼女の顔色が見る見るうちに蒼白になっていった。
「まずい・・・!!」
彼女の胸に耳を当てると辛うじて心臓の鼓動は感じられたが、胸が上下していない。
呼吸が止まっている!!
「オスカル!!!」
彼は指で彼女の口をこじ開けた。
口の中には大量の血。吐ききれずに、喉を詰まらせた。
結核の死亡原因の多くは、喀血による窒息のせいだと彼は知っていた。
彼女の口に自分の口をつけて、彼女の呼吸を止めている血を取り除くべく必死で吸った、そして吐き出す。
満月の月明かりの中、それは狂気の世界だった。彼女を絶対に死なせないという彼の壮絶な愛の姿がそこにあった。
「ふ・・・ふぅーっ・・・」
彼女がひとつ息をした。
「オスカル?」
危なげながらも彼女はなんとか呼吸を取り戻した。
それによって少しずつ顔色が薔薇色に赤みを帯びてくる。
アンドレの目から涙が溢れる。
「良かった。オスカル・・・。良かった・・・。」
アンドレの涙がオスカルの顔に落ちる。
その刺激で薄らと眼を開けたオスカル。
「あ・・・、ア・・・ン・・・ド・・・レ。どう・・・した・・・、何を・・・泣いている・・・のだ・・・?」
オスカルの手がそっと彼の顔に触れる。そしてまた、意識を失っていった。
アンドレはオスカルを抱きしめ、溢れる涙を止められずにいた。
「神よ、感謝致します。オスカルを御許にお連れにならないで・・・。」
駆けつけたマドロンとオスカルを着替えさせ、ベッドに寝かせると、血で汚れた部屋を片付けた。
オスカルは、昏昏と眠っている。
「オスカル様、良かった・・・。」
マドロンはオスカルの身体のあちこちにまだ付いている血を丁寧に拭いてやった。
「アンドレ、私が見ているから、お前も着替えておいで。血だらけだよ。でも、本当によく頑張ったね。私一人だったらどうなっていたことか・・・。ぞっとするよ。」
マドロンもオスカルを亡くしたかもしれない恐怖にまだ震えていた。
「ありがとう、そうするよ・・・。すぐ戻るから。」
それからずっとアンドレは彼女の枕もとについていた。
彼女の意識が戻ったのは、次の朝だった。
「ん・・・・・・?」
そっと眼を開けるオスカル。その蒼い瞳が日の光を吸って見事なサファイヤ・ブルーに輝く。生きて、煌く瞳。生きているからこそ美しい、命の輝き。
「アンドレ・・・。私はどうしたのだ?」
「オスカル、眼が覚めたのか。良かった、本当に良かった。どうだ気分は?」
「う・・・ん。大丈夫、たいしたことないさ・・・。」
力なく微笑んだ。
「オスカル・・・」
「それより、アンドレ。お前は大丈夫か? よく覚えていないが、お前が血だらけだったような気がするのだが。」
「俺が? また夢でも見たのじゃないのか?」
「そうか? ならいいのだ・・・。」
「オスカル、喉が渇いただろう。何か持ってきてやろうか?」
「ん・・・、そうだな。ショコラにしようかな?」
「今、持ってきてやるよ。少し待っていてくれ。」
「うん・・・」
アンドレは部屋を出るとマドロンに自分の代わりにオスカルの側に付いていてくれるよう頼んだ。
「オスカル様。本当に良かった。」
マドロンがオスカルの手を握り、涙を浮かべて言った。
「どうしたのだ、マドロン。何があったのだ? 私はよく覚えていないのだ。血を吐いたのは何とか覚えているのだが、その後一体何があったのだ。」
「オスカル様、私がアンドレの必死の声に気がついてお部屋に入ったとき、あなたは呼吸をしていらっしゃいませんでした。」
「え? 呼吸を・・・」
「そうです。それでアンドレがあなたの喉に詰まった血を吸い出したのです。だから彼も血まみれでした。私は感動致しました。アンドレがオスカル様をどれほど愛しているか・・・。どれほどお大切に思っているか。息を吹き返したあなたを抱きしめて、彼は神に感謝しながら泣いておりました。」
オスカルはマドロンの言葉を聞きながら、涙が止め処もなく溢れてくるのを感じていた。
アンドレがショコラを持って入ってきた。
「オスカル、どうした? 何を泣いている。どこか苦しいのか?」
「違う・・・。アンドレ、ありがとう・・・。助けてくれてありがとう。」
「当たり前じゃないか、オスカル。逆の立場だったら、お前だってそうしてくれるだろう?」
「うん・・・。」
「ちょっと身体を起こせるか? 少しでもいいから、飲んで・・・。」
オスカルの身体をそっと抱き起こすと、背中にクッションを当ててやり、カップを手渡した。オスカルは両手で包み込むようにカップを持って、そっとショコラを一口飲んだ。
「うん、おいしい。アンドレ・・・。心に染み入るようだよ。」
アンドレを見つめて微笑み返す。
「そうか、よかった。」
彼女の笑顔にほっと胸を撫で下ろすアンドレだった。
それから一日彼女はベッドから起き上がれなかった。
それでも、彼女は肖像画の完成を急いで、ベッドの上ではあるがモデルを続けた。
精神的には穏やかに一日を過ごしていた。
その次の朝、彼女は身体がずいぶん軽くなっている自分を感じた。鉛を飲み込んだような身体の重さもだるさも消えて、気力も戻った気がする。
「アンドレ、今日はずいぶんと調子がいいぞ。」
「あんまり油断しないで、まだ寝ていたほうがいい。」
「うん、でも。少し動かないと・・・。動けなくなってしまう。それに、今日中には肖像画が出来上がるといっていたし。」
「失礼します。アルマンですが、入ってもよろしいですか?」
「はい、どうぞ。」
「オスカル様、ご無理なさらずに、ベッドの上で。」
アルマンが彼女を気遣って声をかける。
「いや、今日は気分がいいのだ。椅子に座っていよう。」
「オスカル様、こちらで髪を結ってもよろしいですか?」
マドロンがヘアブラシを持ってやって来た。
「ああ、お願いしようかな・・・。」
静かに、そして穏やかに空気が流れる。
「オスカル様、こちらをお見つめください。後は、その美しい蒼い瞳を描き入れたらお終いでございます。」
「・・・。はい、出来上がりました。まだ、乾いておりませんが、どうぞご覧下さい。」
完成したばかりのオスカルの肖像画を見入る三人。
「ふふ・・・、アンドレ。私がドレス姿で笑っている。お前から貰ったペンダントもあるぞ。なんて幸せそうなのだろう。」
「オスカル、本当に。なんていい笑顔なのだろう。」
「オスカル様、どこから見ても素晴らしい貴婦人です。本当に幸せそうに微笑まれて・・・。」
「ムッシュウ、本当にありがとう。幸せを絵に写し取ったようだ。時間もなくて、苦労を掛けましたが、お陰で私の思った通りの肖像画が出来上がりました。この絵はこのままこの別荘に飾って置きます。いつか・・・、父上や母上にも・・・。」
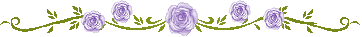
二人はバルコニーに出て、風に当っていた。
アンドレは彼女の腰に手を廻して、抱き寄せた。
「いい風だ。気持ちいいな。オスカル、寒くないか?」
「大丈夫だ。アンドレ、キスして・・・」
「うん、どうした?」
彼は彼女の望みどおりに唇にキスを落とす。
彼の温かい腕に抱かれて、オスカルはしみじみと言った。
「幸せだなって、思って・・・。」
遠くから砂煙りをあげて、一頭の馬が疾走してくる。
「あれ? あれはなんだろう、馬か?」
オスカルがアンドレに聞いた。
「馬みたいだな?」
「こっちにまっすぐ向かってくる。」
「あ・・・!!」
アンドレは、瞬時にすべての事情を察して、天を仰いで目を閉じた。
(来たか、ついに・・・!)
「アンドレ、あれは衛兵隊の制服だ! 誰だろう?」
「・・・・・・」
「あ、アランだ! アンドレ、アランだぞ。アラン、アラン。ここだ。おーい、私だオスカルだ。」
手を振りながら、大きな声でアランを呼ぶ。
その声でアランはバルコニーを見上げた。そして、そこにドレス姿のオスカルを見つけて、呆然とした。
「た・・・隊長? 隊長ですよね?」
「今、降りていくから。」
階下でアランを出迎える、オスカルとアンドレ。
「隊長、休暇中のところ失礼致します。急使にまいりました。連隊本部より出動命令が出ました。フランス衛兵隊2個中隊は、明日、7月13日朝8時テュイルリー宮広場に向けて出動のこと。」
「出動・・・!?」
彼女はアンドレを振り返り、彼の瞳を見つめた。
そこにはすべての覚悟を決めた男の、水のように静かな瞳があった。
彼は何も言わず、頷くように眼を閉じた。
「7月13日、明日か・・・。わかった。私が戻って直接の指揮を執る。すまんが、先に戻って、ダグー大佐に将校を集めて2個中隊を選んでおく様に伝えてくれ。遠いところご苦労だった。少し休んで、馬を替えていくがいい。私も後を追う。」
「わかりました。アラン・ド・ソワソン、本部に戻りそのように伝えます。」
敬礼する。
「でも、隊長・・・。」
「何だ?」
「その台詞、その格好には似合いませんぜ。」
「え? あ、そうか、そうだな・・・」
赤面するオスカル。
「ええい、うるさい!! 余計なお世話だ! アンドレ、馬を替えてやってくれ。」
「わかった。」
「それじゃあ、隊長。」
「うむ。また後で。夜中には着けるようにするから。」
「はい、隊長もお気をつけて。」
アランが一足先にベルサイユに戻っていった。
ただ、黙ってその後ろ姿を見つめる二人。
歴史は今大きく変わろうとしていた。
−つづく−




