別荘に戻った二人に、マドロンが待ち構えたように声をかけた。
「オスカル様、お帰りなさいませ。画家のアルマン様がそちらのお部屋でお待ちでございますが。」
「え、画家の? わかった。今行くよ。」
オスカルが扉を開けて中に入ると、アルマンは即座に立ち上がった。
「これは、どうもお待たせして・・・。」
「オスカル様、ご結婚おめでとうございます。」
突然の祝いの言葉にオスカルは少し面食らったまま礼を言った。
「どうもありがとうございます。」
「お召し物のせいでしょうか? それともお幸せだからでしょうか? 随分と雰囲気が違われて・・・。以前は氷の花のようでいらしたのに、今は匂い立つ薔薇の花のようでございます。」
慣れない女性としての誉め言葉に、オスカルは頬をほんのりと染めた。
「いや・・・、そんな。あ、どうぞお掛けください。」
慌てて彼に椅子を勧め、自分も反対側の椅子に腰掛けた。
「申し訳ありませんでした。自分から肖像画をお願いしていたのに、急にいなくなってしまって。」
「いいえ、あなた様は絵のモデルになられるのがお嫌いだとベルサイユでも評判でございました。そのお方を描かせて頂いていたのですから。是非、絵を仕上げたいとこうしてお伺い致しました。あと、ほんの少しで仕上がります。それに私は出身がこちらでございますので、どうぞお気になさらないでください。」
「そうですか、絵を仕上げて頂けるととても有難いです。私も気にしていたのですが、もう諦めようかと思っていたのです。お言葉に甘えて、もう一つお願いがあるのですが。」
「はい、なんでございましょう?」
「もう一枚、描いて頂けませんか? 今度は軍服姿ではなく、ドレス姿で。」
「もちろん、喜んで描かせて頂きます。」
「ただし、時間がないので、かなり急いで仕上げてもらいたいのです。」
「はい、それではすぐ取り掛かってもよろしいでしょうか?」
「そうですね。早速お願いします。」
「前の絵を先に仕上げてしまいましょう。」
「オスカル、あまり無理をしないように。」
彼女を気遣いアンドレが声をかける。
「うん、わかった。でも・・・。急ぐのだ・・・。」
彼女には命の終わりを告げる砂時計の、砂の落ちる音が聞こえてくるようだった。
「今日は、私も疲れましたし、ここまでに致しましょう。」
アルマンがオスカルを気遣い、そっと絵筆を置いた。
「それで、一枚目の絵は仕上がりましたが、いかが致しましょうか?」
「その絵はジャルジェ家へ届けて欲しいのだが、良いだろうか?」
「わかりました、私が責任を持ってお届けします。それでは、また明日お伺いします。」
アルマンは画材を片付けると、静かに部屋を後にした。
「オスカル様、遅くなりましたが、お食事はこちらにお持ちしましょうか?」
マドロンがオスカルを気遣い、声を掛けた。
「ああ、そうか。食事がまだだったな。気が付かなかった。アンドレ、お腹すいただろう。私は欲しくないから、アンドレの分だけ持ってきて貰おうか。」
「だめだ、オスカル。無理をしてでも食べなくては。」
「わかった。じゃあ、スープだけ貰おうかな?」
「そんな、オスカル様、せめて卵料理だけでも。卵がだめなら何か他に食べられそうなものはございませんか?」
「そうだよ、オスカル。もう少し食べて栄養をつけないと。」
「ごめん。ちょっと食べられそうもないのだ・・・。」
「わかった・・・。」
アンドレは彼女の肩に手をおくと辛そうに眼を伏せた。
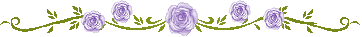
アンドレは夜着に着替えたオスカルをベッドに休ませると、彼女の前髪を上げ、額にやさしくおやすみのキスをした。
「今夜はゆっくり休め・・・。ん・・・? オスカル、お前少し熱があるぞ。」
アンドレは慌てて彼女の額に手を当てた。
「いいのだ、アンドレ。」
額に置かれた彼の手を掴むと、自分の身体に彼の腕を廻し、自分からそっと唇を重ねていった。
「アンドレ・・・、アンドレ・・・、あ・・・あ・・・、愛している。」
昨夜とまるで違う自分を感じた。
(昨夜までの私は、真実の男の愛がどんなものか知らなかった。私は何と愛されているのだろう。)
愛しい人に身も心も愛される喜び、彼の愛に溺れていく。女として、自分が変わっていく。
オスカルは愛する人の手で、また新しく生まれ変わる自分を感じていた。
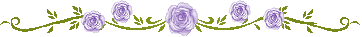
「ア・・・アラン! ラサール! フランソワ! あーーっ!」
「オスカル! オスカル、どうした!」
アンドレは眠ったまま涙を流し、悲鳴をあげる彼女を揺り起こした。
「アンドレ! ああ、よかった。夢か・・・。夢だな?」
「夢だよ、オスカル。何も心配はいらない。どうしたのだ?」
震える彼女を抱きしめ、背中をやさしく撫でてやる。
「み、皆が撃たれて・・・。衛兵隊の皆が・・・。血まみれで・・・死んでしまった・・・。
私は彼等を助けられなくて・・・」
まだ悪夢の興奮からか、涙が、身体の震えが止まらない。
「彼等は衛兵隊の皆は、どうしているのだろう。私が彼等を見捨てて、逃げたと思っているだろうか・・・? パリは、ベルサイユはどうなっているだろう・・・。自分だけが、幸せで・・・。安穏としていて・・・。」
「オスカル・・・。」
彼女の辛さが充分に理解できるだけに何も言葉にできない自分がいた。
何と慰めても、上辺だけの言葉になるだろう。結局黙って抱きしめてやることしか自分にはできない。
「アンドレ、私が今まで男として生きてきたのは、何の意味があったのだろう? 私がこの時代に軍にいるということは、何か大きな意味があるような気がするのだ。私だからこそできる何かが。」
「お前だからできること?」
「そうだ。それが何かまだわからないが。でも、今の私の身体ではそれがわかったとしても、できるのかどうかもわからないが。」
オスカルの蒼い瞳は、空を彷徨い、深い湖のように、静かな光を湛えていた。
オスカルは自分の成すべきことを静かに考えていた。
やりたい事ではなく、やらねばならぬこと。
自分のできることではなく、自分がやり遂げなくてはならないこと。
残り少ない命ならば尚のこと、悔いの無い人生を送りたい。
自分の人生を完全に昇華させたい。
でも、簡単にその一歩を踏み出せないのは、愛しい人の人生までも終わらせてしまう可能性があるということだった。
「オスカル、何を考えている?」
アンドレがそっと声をかける。
「いや、別に・・・。なんでもない・・・」
彼女は静かに微笑んだ。
(言えない、彼には絶対に言えない。言ってしまったら彼はきっと・・・。)
(オスカル、お前は・・・。やっぱり俺には止められないのか・・・。)
二人は黙って抱きしめあったまま、互いに相手の心を推し量り、思いやり、そして互いにつらい時間をベッドの上で過ごしていた。二人共眠れなかった。
「オスカル、眠れないのか?」ついにアンドレが口を開いた。
「お前もだろう? アンドレ。」
「そうだな、星でも見ようか?」
二人は夜着を着るとバルコニーへ出て、空を仰いだ。
「最近はゆっくり星を眺めたこともなかった。満天の星空か・・・、ああ、きれいだ。あの星の瞬き、人間にはほんの一瞬に思えても、星にとってはきっとものすごく長い時間なのだろう。人間の一生なんて、星の瞬きほどのものかも知れ
ないな、オスカル。」
「ふふ・・・、今日は詩人だなアンドレ。そういえば、恋をすれば犬も詩人だって誰かが言っていたな。」
「こら、からかうなよ。」
彼女の頭を掴み、自分の肩に凭れかけさせる。
「お前の思うように生きろ。俺は、お前の影だから。」
彼女に聞こえないような小さな声で呟いた。
「え? 何か言ったか?」
「いいや、何も・・・。」
そういいながら彼女の唇を捕らえるとやさしくくちづけた。
そして抱きかかえるとベッドに運び、
「オスカル、少しでも休んだほうがいい。大丈夫だ、俺がいるから。怖い夢な
ど見たいように、ずっとついているから。」
と眠るように促した。
「うん・・・。」
眼を閉じた彼女の頭をアンドレは優しく撫でてやった。彼女が眠りに落ちるまで、ずっと・・・。
次の朝、朝食を済ますとアンドレが言った。
「オスカル、もうすぐ画家の先生がお見えになるだろう。その間俺はちょっと出かけて来たいのだが、かまわないか?」
「別にかまわないが、どこへ行くのだ?」
「ないしょだよ。すぐ戻るから。」
彼女の頬にキスして急いで出て行った。
「マドロン、今日は髪を結ってくれ。絵に残すのなら、そのほうがいいだろう? ただし、あんまり引っ張らないでくれよ。痛いからな。」
「もちろんでございます。お任せください。」
「ムッシュウ、待たせたね。」
「これは、これは・・・。結い上げた髪もお似合いでございます。」
「悪いね、急がせてしまって。」
「いいえ。私は本当に幸せな画家でございます。こんな素晴らしいモデルを描けるのですから。どうぞ、お楽になさっていてください。」
「そうか、ありがとう」
ゆっくりと静かな時間が過ぎていった。
オスカルが眠そうに頭を振る。
「お疲れですか? 終わりにいたしましょうか?」
「いや、すまん。ちょっと眠かっただけだ。」
「オスカル、ただいま。」
アンドレは書類や冊子をたくさん抱えて帰ってきた。
「お帰り、アンドレ。何だ? 何を持ってきたのだ?」
「これだ。目を通して置くといい。」
持っていた物をオスカルに渡した。
「これは、ベルナールのアジビラに、こっちはロベスピエールの演説原稿か? それから、現在のパリ及びベルサイユの状況。」
彼女の眼が生気を放って輝く。
「アンドレ! ありがとう。私が一番欲しかったものだ。」
人目を忘れてアンドレに抱きついた。
「でも、どうやって・・・?」
「忘れたのか? ロベスピエールはアラスの出身だって。それにベルナールとも元々知り合いだし。ここは、パリから離れている割には情報が手に入り易いのさ。」
「そうか、そうだったな。」
オスカルは早速書類に目を通し始めた。左手で額を押さえながら眉間に皺を寄せ、難しい顔で。書類を読むときの彼女の癖なのか、司令官室で見られたいつものポーズ。
「おい、オスカル。お前自分の姿わかっているのか。軍服じゃないのだぞ。」
「え? 何か言ったか?」
彼女は自分が今モデルをしていることも、自分がドレス姿であるということも、すっかり忘れていた。
(ああなると、何も聞こえないんだよな、オスカルは。本当はもうひとつプレゼントも買ってきたのに。アジビラのほうが好きそうだな、お前は。)
アンドレはため息を一つ漏らすと、オスカルを見つめていた。
−つづく−




