「アンドレ、私は今休暇中なのだな? もちろん軍籍も衛兵隊に在るわけだ。」
オスカルは、まっすぐ彼の瞳を見つめて静かに言った。
「そうだ・・・。オスカル、俺は・・・。」
「いいのだ、アンドレ。もう何も言うな。お前の気持ちは痛いほど分かっている。でも、私の気持ちも分かっている筈だ。もう、誰であろうと私を止めることはできない。」
彼女はきっぱりと言い切った。
「オスカル・・・」
「アンドレ、来て。」
オスカルはアンドレの手を掴むと、階段を昇り、部屋に入った。
そして、後ろ手に鍵を掛ける。
部屋の中は夏の日差しが入り込んで眩しいほどだった。
オスカルは、彼を長椅子に座らせると、自分は立ったまま窓から差し込んでくる眩しい光の中に向かい、アンドレに背に向けた。結い上げた髪のピンを外し、髪を解いていく。そして、すべてのピンを外し、頭を振る。黄金の髪がふわりと肩に広がった。
「オスカル・・・?」
アンドレは、自分の目の前での光景が信じられなかった。
オスカルはドレスの背のボタンを外し、そっと肩から滑らせた。
下から現れたコルセットの紐を緩めて、下に落とす。
そして、躊躇せずに最後の下着を脱ぐと、アンドレに向き直った。
太陽の光を背に受けて、生まれたままの姿のオスカルがそこにいた。
眩しいほどに美しい女性(ひと)がそこにいた。
「アンドレ、私を見て・・・。私を覚えておいて・・・。お前だけに覚えていて欲しいのだ。女としての私のすべてを。」
眩しい光を反射する豪華な黄金の髪、深い海の底を思わせるようなサファイヤ・ブルーの瞳、鮮やかな深紅の薔薇のような唇。華奢な首筋から続く、滑らかな肩、そして誇らしげに天を仰ぐ二つの柔らかな乳房、それを彩る淡いピンクのつぼみ。無駄な肉のまるでない見事なまでの細腰。彼女自身を覆う黄金の叢。引き締まった臀部。すらりと伸びた長い足。そして、陶磁のようにしみひとつない滑らかな白い肌。
アンドレの視線と夏の太陽がオスカルの身体を刺すようだった。
「背中も見せて、オスカル。髪を上げて・・・。」
彼の望み通り、彼に背中を向けると、両手で髪を持ち上げる。彼女の産毛が太陽の光を吸収して、全身がきらきらと黄金色に輝く。
「綺麗だ・・・オスカル・・・」
「アンドレ・・・。」
アンドレは黙って立ち上がると、身に付けていた衣服をすべて脱ぎ捨てた。
そしてオスカルに向き直った。二人はしばらくお互いをただ見つめていた。
地位も身分も肩書きも、何も纏わない、生まれたままの二人。
視線を絡ませたまま互いに歩を進め、向き合うとそっと手のひらを合わせた。
二人は何も語らずとも悲しい運命を感じていた。
まったく先の読めない明日。
これから命を賭して勝ち取ろうとしているもの。
そして、そのために手放さなければならないもの。
守らなければならないもの。
だからこそ今だけは、ただの男と女として――。
アンドレは自分の魂の半身をその胸に抱きしめ、そっと口づけた。
オスカルはゆっくりと睫毛を伏せると、愛しい人の口づけを受けた。
そう、アダムとイヴが初めて交わしたキスのように・・・。
声にはならない声で『愛している』と何度も何度も囁きながら口づけを繰り返す。
迸るような愛をお互いの身体で確かめ合うかのように。
熱く、甘く、強く、そして激しく。その情熱の命ずるままに。
いつしか、大きな快感がうねりのように彼女を襲う。
彼の激しい動きに彼女の髪が大きく揺れる。
彼の愛に翻弄される。
オスカルは自分のすべてが開放されつつあるのを感じていた。
(私は女だ・・・、今・・・、こんなにも女だ・・・)
オスカルの眼から一筋涙が毀れ、その瞬間彼女の身体から力が抜け、意識を失った。
アンドレは彼女の身体を逞しい腕で支えると、抱き上げて長椅子に座った。
そして、彼女が気付くまで、抱えたまま口づけを繰り返し、やさしく髪を撫でていた。
アンドレは、彼女の左肩の刀傷に愛しそうに口づけた。
「オスカル、この傷は俺がお前を守れなかった証しだ。あの日、俺はどれほど自分の武力のなさを呪ったことだろう。俺の命はすでにお前のものだ。だからどこへでも行くがいい、たとえ地獄の底へでも。俺はお前と共に行く。」
「あ・・・、アンドレ・・・?」
「綺麗だったよ、オスカル。全部見せて貰った。絶対に忘れない。」
「うん。」
二人はお互いを見つめ合ったまま、静かに微笑み、束の間の優しい時間を過ごした。
そして、ついにオスカルが口を開いた。
「アンドレ、私の軍服を出してくれ。お前のことだ、すべて持って来ているのだろう?」
「すべてお見通しだな。」
「ふふ・・・、付き合い長いからな。」
アンドレは、彼女の軍服、ブラウス、キュロット、軍靴、手袋、剣そして拳銃を持ってきた。
「ありがとう。お前も着替えてくるがいい。それとカーヴ(ワイン貯蔵庫)に行って1755年もののボルドーの赤、確か"サンテミリオン・グラン・クリュ"があった筈だ。一本持って来てくれ。それとデカンタとグラスを二つ。」
「わかった。少し待っていてくれ。」
オスカルは一週間振りに軍服に袖を通した。
「ん? ちょっと緩いな。そんなに痩せたか? でも、久しぶりに気持ちがしゃんとする。ふふ・・・結局私はこっちのほうが落ち着くのか? 我ながら情けないな。そうだ、これは、もういらないな。」
オスカルは勲章と階級章を外し、何の飾りも付いていない自分の軍服姿を改めて眺めた。
「よし、後は・・・。あれを・・・・・・。」
彼女の瞳が哀しく光った。
「オスカル、持って来たぞ。」
「ああ、ありがとう。そこに置いてくれ。私がデカンタージュするから。」
ワインのコルク栓を開け、静かにデカンタージュする。
「せっかくのボルドーの年代もののワインなのだから、もうちょっと寝せておく時間があるといいのだが。急だったし、仕方がないな。」
デカンタからそっとグラスに注ぐ。
二人は並んで長椅子に座った。オスカルは一つのグラスをアンドレに渡し、自分もグラスを持った。
「アンドレ、乾杯しよう。私の生まれた年のワインだ。まだ飲んだことがなかったのだ。何かの時にと飲まずに置いておいたのだ。もう少し空気に触れさせて、落ち着かせてから飲みたかったな・・・。」
二人はグラスを静かに合わせて、互いに見つめあいながらワインを口にした。
「うん、なかなかいいな・・・。私と同じ年のワインか・・・。」
「そうだな。」
二人はそれ以上話す言葉が見つからなかった。
アンドレはオスカルをそっと引き寄せて、静かなくちづけを贈った。彼女もそれに答えて、くちづけを返す。やさしいキスだった。
「アンドレ・・・」
静かな、本当に静かな声で彼女は言った。
「うん? 何だ。」
「今まで、どうも・・・ありがとう・・・。お前の・・・お陰で、この一週間、私は・・・本当に・・・本当に幸せだった・・・。」
彼女は俯いたまま、くぐもった声で言った。
肩が少し震えている。
「どうした、改まって。オスカル、お前泣いているのか?」
俯いたオスカルの顔を両手で挟んで上げさせると、彼女の瞳は涙で濡れて、光っている。涙を耐える為か、下唇を赤くなる程噛み締めていた。
「泣いてなんかいない・・・。」
彼の手を振り払うと立ち上がった。
「おい、オスカル! 本当に変だぞ。どうしたのだ。」
アンドレは、様子のおかしい彼女の後を追おうと、椅子から立ち上がろうとした。しかし、身体が言うことを利かない。身体に力が入らない。彼の手からワイングラスが滑り落ち、音を立てて砕け散る。
「し、しまった!!! オスカル、お前、薬を使ったな?」
意識が朦朧とし始める。
「すまない、アンドレ。以前ラソンヌ先生から貰った睡眠薬だ。アンドレ。私はお前だけは死なせたくないのだ。お前に助けて貰ったこの命だけれど、私は一人で行くよ。」
「オスカル、だめだ! 一人では・・・行かせ・・・ない、絶対に・・・。どうし・・・ても行く・・・と言う・・・なら、俺を・・・殺して・・・行って・・・くれ、オ・・・ス・・・カ・・・ル・・・。」
「アンドレ、私のことを覚えていてくれるのだろう? 女としての私を・・・。お前だけが知っている、私を・・・。」
「オ・・・ス・・・カ・・・ル・・・」
彼は必死で探した。彼女と自分を繋ぎ止める何かを。
「アンドレ・・・、さよう・・・なら。愛しているよ。永遠に・・・。」
彼女はアンドレに最後の口づけを贈る。
愛しい人へ万感の想いを込めて。
「オス・・・カ・・・ル、待・・・て・・・、あ・・・」
彼の意識はついに途切れた。
彼女の目から滑り落ちた一粒の涙が彼の頬に落ちた。
眠りに落ちた彼の頬を愛しそうに指で撫でると彼に最後の言葉を告げる。
「私は行くよ、アンドレ。パリへ。私の行くべき場所へ。」
オスカルは、涙を拭くと、決して振り返らずに部屋を出て行った。
階下ではマドロンが泣いていた。
「マドロン、泣かないで。いつもの仕事だ、すぐ帰ってくるよ。アンドレと二人で待っていておくれ。今回はアンドレを連れて行かない。私だけの仕事だから・・・。今まで世話をかけたね、ありがとう。」
オスカルは彼女の頬にやさしくキスをした。
「オスカル様、いってらっしゃいませ。お気をつけて。お帰りをお待ちしております。」
涙を堪えて、オスカルを送り出す。
もう二度と見ることの出来ないであろう人の凛々しい姿をその目に焼き付けて。
オスカルは、馬に跨り、一度だけ別荘を振り返った。
さようなら、女として幸せだった私。
アンドレと二人で穏やかな《もうひとつの人生》を選ぶこともできた。
でも、私は自分の使命を果たしに行く。
そのために今まで男として生きてきたのだと思うから。
初めてだな、アンドレ。側にお前がいないのは。
お前は生きて、幸せになってくれ!
私の最後の願いだ。
彼女の瞳は、遠くを見据えていた。
自分の命より大切な、愛しい人とも別れた。
もう決して、涙することはないだろう。
そして、真っ直ぐ馬を駆り、彼と二人で来た道を、今一人でベルサイユへ向かった。
愛しい人との思い出だけを胸に・・・。
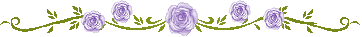
ベルサイユの連隊本部に到着したのは、真夜中だった。
真っ直ぐ、司令官室に向かう。
「隊長、遠いところご苦労様です。」
「ああ、アランか。先ほどはご苦労だったな。」
「あの、お一人ですか? アンドレは?」
「彼は除隊させた・・・。」
「え?」
「あいつのことは、もう言うな。」
オスカルは無表情のまま、去っていった。
「隊長・・・。」
(どうしたんだ、隊長は。アラスで最後に会った彼女は、姿は違ってもいつもの隊長だった。あの冷たさは何だ? まるで抜き身の刀身のようではないか。触ったら、切れてしまいそうだ。いつもの隊長ではない。アンドレ、お前はどうしたんだ? この一番危険な時に、隊長を一人にして。何があった、アンドレ。)
「隊長、ご苦労様です。」
ダグー大佐が出迎える。
「すまなかったな。こんな時期に一週間も休暇を取って。」
「いいえ、隊長。それで早速ですが、お言葉どおり、2個中隊は選んで置きました。しかし、たかが2個中隊の指揮に隊長が直接お出でにならなくとも。将校は他に大勢いるではありませんか。」
「いいのだ。誰が行ってもつらい状況になるだろう。それならば私が行く。私の部下達だからな。」
「隊長。」
「すまんが、現在の他の部隊の状況を教えてくれ。現在のパリにどれだけの部隊が集まっているのか。それと今日までの市民側の動きを。」
7月11日、国王は財務長官ネッケル氏を突然罷免し、プルトゥイユ男爵を任命した。そして、7月12日その知らせを受けた、ベルナール・シャトレが《武器を取れ! シャン・ド・マルスのドイツ人部隊は今晩パリに入って、住民を刺し殺すぞ。記章を付けよう!》と演説した。
民衆は熱狂し、各地で小競り合いが生じ、死傷者も出た。
パリにいた国王軍の司令官は、午後シャンゼリゼにスイス兵一連隊と大砲を4門配置した。夕方群集と小競り合いを起こし、銃声がとどろき、警鐘が鳴り響いた。この暴挙の知らせはパリ中に知れ渡った。人々は市庁舎に駆けつけ、武器を要求し、武器商を襲った。
たった一晩でパリは混乱状態になった。
パリとベルサイユの間に配置された軍隊は約10万。
総司令官はド・ブロイ元帥。
テュイルリー宮広場には、ランベスク公ひきいるドイツ人騎兵隊。
ルイ15世広場には、ブザンバル侯指揮下の竜騎兵。
スイス人傭兵。フランス歩兵。
1789年7月13日 月曜日 早朝
パリ市民は鐘や太鼓の音で目を覚ました。国王軍が鎮圧のためにパリを包囲し
たというデマが流れた。緊張と興奮が走り、既に「革命」の兆しが見えてきた。
「隊長、着剣完了。整列終わりました。」
「始めにいっておく、何があっても必ず私について来てくれ。いいか何があってもだ。前進・・・・・・!!」
−つづく−
イラスト「光の中で」はこちら




