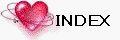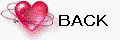その日から、オスカルの地獄の日々が始まった。
子供のころから父に鍛えられていたオスカルではあったが、レジーの厳しさはオスカルの想像を絶するものだった。
まず、朝一番で、森の中を5kmほどランニングする。
レジーも通常のトレーニングの一部らしく、一緒に走っている。
「遅いぞ、この程度走れないでどうする。基本体力も足りないな。」
レジーは息も上がらず、汗一つかかないで、平然と走っている。
彼は普通に道を走っているオスカルと違って、森の中の切り株や倒木などわざと障害になるものに向かって走っている。金の長い髪をなびかせ、平然と障害を飛び越え走り抜ける豹のような敏捷な彼の動きをオスカルは憧れと羨望の眼差しで見つめていた。
そして、続けて柔軟の運動。
関節や筋等を柔軟にしておかないと、ケガも避けられないし、第一上達が望めないとレジーは彼女に教えた。彼女自体特に身体が固い訳ではないが、レジーの望む柔軟性はかなりのものだったので、痛みはものすごいものだった。彼は決して手加減をしてくれず、涙が滲むほど痛かった。
レジーにとってはただの準備運動というべき、この二つが終わったとき、オスカルは既に疲れていたが、涼しい顔をしている彼の顔を見ると負けてたまるかと気合を入れた。
「ほら、もうギブアップか? 剣が下がってきているぞ。両手使うというのはその程度か? だめだ、やっぱり左手が弱すぎる。」
レジーは幅10cm程度のベルトのようなものを持ってくるとオスカルの両手首に嵌めた。
「うわっ、重い。」
「ベルトに鉛の板を仕込んである。慣れないうちはかなり辛いと思うが、しばらくすれば慣れる。左腕の筋力が弱すぎるから、倍重くしてある。これをつけたまま練習して貰おうか。」
「これをつけたまま?」
「そうだ、一日中だ。何をするにもそのままだ。出来ないのか? 出来ないなら、さっさと泣いて帰れ。」
「いやだ! 誰が帰るものか。」
「そのまま、かかってこい。まず左手だ。」
レジーは剣を抜くと左手に持ち替えて、オスカルと剣を合わせた。
オスカルの腕が手にした剣と付けられた鉛入りのベルトの重さに段々と耐えられなくなり、上がらなくなってくる。けれどレジーは少しも容赦せず、剣の練習を続けさせた。オスカルはただ意地だけで、立っていた。息が上がり、全身汗びっしょりでふらふらになってもレジーは止めさせなかった。
「待って・・・、水を・・・。」
荒い息のまま、床に膝を突くと彼女は言った。
「水? 甘ったれるな。」
レジーは側にあった水桶を掴むとオスカルの頭から水を浴びせ掛けた。
「・・・・・・、畜生!」
水を浴びせられた屈辱に、レジーを睨み付けたオスカルの蒼い瞳が鋭い光を発し、瞬時に色が変わった。彼女が本気で怒ると蒼い色が薄くなり、冷たそうなアイス・ブルーに変化する。それを知っているレジーのすみれ色の瞳が光った。
(そうだ、オスカル。その眼だ。その眼が欲しかった。)
金の髪に水を滴らせて、立ちあがると最後の力を振り絞り、レジーに立ち向かった。いつもの彼女の剣とはまるで違う、殺気さえも孕んだ鬼気迫る剣捌きだった。レジーも圧倒されるほどのオスカルの気迫。しかし、ついに剣が彼女の手から滑り落ち、オスカルは意識を失った。床に崩れ落ちる寸前で彼女を抱きとめると、軽く抱え上げて2階のベッドまで運んだ。
「良くがんばったな・・・。オスカル。」
レジーは彼女の顔を愛しそうに見つめ、小さな声で囁いた。
しばらくして彼女が気が付いたとき、濡れた服は着替えさせられていた。そのことに彼女が抗議しても彼は平然と受け流した。
「言った筈だ。ここでは男と女ではないと。約束する、何もしない。そんな浮付いた気分で俺もここにいる訳じゃない。でも、お前の身体を見ることは悪いとは思うがこれからもあるだろう。ドレスの着つけの為にコルセットを締めるのも他に誰もいないし、お前一人では出来ないだろう。俺がするしかない訳だからな。それでも良いか?」
オスカルは彼の真剣な表情を見て、納得するしかなかった。
「よし、では今度は貴婦人のためのレッスンだ。起きろ、ドレスに着替えるぞ。」
レジーは、オスカルを鏡の前に立たせた。
「取り敢えず基本はやっぱり、ローブ・ア・ラ・フランセーズだろうな。此の手のコルセットにも慣れなくてはならないし。ところでお前ドレスは何回くらい着たことがある?」
「あの、この間会った時と、あと一度だけ・・・。」
「結局2回だけか・・・。それは何と言うか、絶望的だな。コルセットも慣れないとかなり苦しいからな。剣よりこちらの方が辛いかもしれないぞ。しっかり立っていろよ、締めるぞ。」
レジーは、コルセットの紐を締め上げた。
「うわっ、い、息が出来ない・・・。」
「後でもっと辛くなってくるぞ。これでもまだ普通より締め方が緩いのだからな。」
「これで?」
「そうだ。まあ一種の拷問のようなものだな。段々と絞まってくるような気がするから。今日は髪はこのままでいいか。」
レジーはドレスの後ろを止めてやると
「さて、出来た。格好だけは貴婦人だな。まずはこのまま食事だ。」
「ええっ、この格好で食事するのか?」
「普通の貴婦人はみんなそうだぞ。」
「それは、そうだが・・・。」
内心おもしろくなかったが、逆らう訳にも行かなかったので黙ってレジーの後をついていった。
「下へ行くぞ。」
そう言って振り返ったレジーはオスカルの歩き方を見て、ため息をついた。
「歩き方の練習からだな・・・。それではどう見ても女装の男だ。そんなに大股で歩くな。軍服じゃないのだぞ。」
「うわっと。」
自分のドレスの裾を踏んづけ、前につんのめった彼女の腰をレジーが瞬時に片手で支えた。
「あーあ、頭が痛くなってきた。まったくどうしてお前がこの仕事を引き受けたのだ。確か、女性という条件が付いていた筈だ。」
「知るものか、私は名指しされたから、来ただけだからな。」
急にオスカルはあることに気が付いて彼に尋ねた。
「そうだ、このドレスは私のサイズで作ってあるみたいだが、どうして私のサイズが解ったのだ?」
「諜報部に解らないことがあると思うか? もっともお前のスリーサイズなんて、調べなくても解るけど。そうだな上から87、63、90cm、体重は58キロといったところか?」
レジーは得意そうに言った。
「ば、ばか。違う・・・」
オスカルは言い当てられて、真っ赤になって言い淀んだ。
オスカルは食卓に付いても、まったく食欲がなかった。疲れ果てていたせいもあるし、コルセットも辛かった。
レジーは、そんな彼女を見て、
「一日目でもうへばったのか、だらしないな。コルセットが苦しくて食べられないようなら、この先仕事にはならないし、帰るか?」
「へばってなんかいない、ちゃんと食べられる!」
レジーの挑発的な物言いにオスカルは無理して口に押し込んだ。でも、実際は余りの疲労に吐き気さえ催していた。レジーもそんな彼女の状態は解っていたが、食欲のないまま食べないでいたら、完全に参ってしまうので、彼女を怒らせてでも、食べさせたのだった。
二人は早々に食事を済ますと、ダンスのレッスンの予定を諦め、歩き方の練習から始めた。
「軍足じゃないのだぞ、華奢なヒールだ。もっと歩幅を小さく。ドレスは端をそっとつまんで優雅に歩くのだ。」
「どうして、こんなつまらない練習をしなくてはならないのだ。」
オスカルは全然思うように歩けなくて、いらいらしていた。
「ばか、貴族の貴婦人がそんな歩き方をするか。一目で偽者だとばれる。貴族の令嬢には間違いはないのに、どうしてこんなに苦労しなくてはならないのだ。」
「・・・・・・」
「もう1回、あちらの隅まで行って戻って、そこの椅子に座る。」
オスカルは言われた通りに歩き、椅子に座った。
「こら、大股開いて座るな。」
「どうせドレスで隠れて見えないではないか。」
「見えてなくても、解る。膝は揃えて、閉じろ。ああ、そうだ。もう一つ大事なことを忘れていた。男言葉で話すな。」
「解った・・・。気を付ける。」
「解ったじゃない、解りましただ。その言葉遣いで努力はパーだ。お前の身近にお手本となるべく、素晴らしい貴婦人がいるだろう。所作、言葉遣い共に良く思い出せ。」
「貴婦人?」
「解らないか? ジャルジェ夫人だ。」
「母上か・・・。そうだな、素晴らしい貴婦人だろうな、優しくて、控え目で、穏やかで・・・。私にはないものばかりだな、母娘だというのに・・・。私は母上と娘としての時間を持ったことがないからな・・・。」
今まであまり考えたことのなかった事実に思い当たって、オスカルは視線を落とした。
「すまない・・・。オスカル・・・。」
「いや、いいのだ。気にしないでくれ。」
「今日は、ここまでにしよう。」
レジーは、オスカルのドレスを一人で脱げるように後ろだけ外し、コルセットの紐を緩めてやると、部屋を出ていった。
オスカルは身体を締め付けていた物を全部脱ぐと、夜着に着替え、よろよろとベッドに倒れ込んだ。身体中の筋肉が悲鳴を上げていた。
まだ痛みはそれほどでもなかったが、全身がだるく、自分の身体とは思えないほど重かった。明日には凄まじい筋肉痛に襲われるだろう。疲れにすぐうとうととした彼女の耳にドアをノックする音が聞こえた。
「レジー? 鍵は掛かっていない・・・。」弱弱しい声でやっと答えた。
オスカルにはもうベッドから出て、立ちあがる気力も体力も残っていなかった。
「入るぞ、オスカル。」
部屋に入ったレジーは、オスカルがベッドに入っているのを見て、
「そのまま、寝ていろ。」
と言うとレジーはつかつかとベッドに近づき、彼女の腕を掴んだ。一瞬身体を固くして怯えた彼女に、
「安心しろ、マッサージにきただけだ。このままだと、明日筋肉痛で動けなくなるからな。ちょっと痛いぞ。」
ベッドの端に腰掛け、彼女の固くなった筋肉を暖かく大きな手でやさしく揉み解して行った。口では酷いことを言いながらも、レジーは結局彼女のことだけを考えているのだった。
「レジー、ありがとう。昨夜も嬉しかった・・・。」
「このまま、眠れ。明日も大変だから・・・。」
オスカルは彼の気持ちが嬉しかった。やっぱりいつもの彼だ。
何も心配することはないのだ。安心したオスカルは、睡魔にあっという間に襲われ、眠りに落ちた。
オスカルが眠ってからもレジーはマッサージを続けていた。
オスカルの意地っ張りなところを利用して練習させたので、少し無理をさせ過ぎたかなと思っていた。筋肉の張りはレジーが思っていたよりも酷く、全身に及んでいた。かといって、明日からのトレーニングを軽いものに変えてやる訳には行かない。結局は彼女の為なのだ、心を鬼にしてやり遂げなくてはならない。
(オスカル、俺だって辛いのだぞ。こんなこと俺の本意ではないのだから・・・。)
レジーは充分なマッサージを彼女に施すと、上掛けをきちんと掛け直してやり、部屋を出ていった。
オスカルは朝起きて思ったより身体が辛くないことが、不思議だった。疲れていてすぐ眠ってしまったので、レジーがそんなに長い時間自分の為にマッサージを続けていてくれたことに気が付いていなかった。
その日から、受身の練習を増やした。
最終的には投げ技も完成させるつもりだが、投げる前に投げられること、そしてその前に受身をというのが、レジーの持論だった。床で受身の練習をさせたら、1日であざだらけになるので、大きなマットを敷いた。
取り敢えず完璧な受身が取れれば、大きなケガをすることもない筈なので、彼女の身体が打ち身であざだらけになっても、受身の練習を続けさせた。
かなり受身が上達したと感じたら、今度はずっと投げられるという地獄がオスカルを待っていた。レジーに近づいただけで投げられているような気がしていた。いつ彼が自分に触ったのかさえ、解らないような投げられ方だった。余りの投げ技の早さに受身が取りきれず、身体をしたたかにマットに打ち付け、何回か気を失った。
オスカルにとって気を失っているのは、とても喜ばしいことだった。その間はトレーニングを少しの時間でも、休めるからだった。意識がある限り、レジーは絶対に休ませてくれなかった。
相変わらず、手首に付けている鉛の板は重い。
付けたままの生活は既に4〜5日経過しているが、まだレジーの言うようには、少しも楽にならない。それどころか、あまりにもハードなトレーニングが続くため、尚一層重さが身に染みるのだった。
オスカルは夜がくるのが、待ち遠しかった。彼の「今夜はここまで」という言葉が心底うれしかった。食欲など当の昔になかったが、意地で何とか口に押し込んでいた。食べられなければ完全に参ってしまう。ふと気が付けば、自分の身体はかなりの部分に無数のあざが出来、色が変わっていた。立っているだけで、身体のあちこちが痛んだ。オスカルは弱音を吐きそうな自分を何とか奮い立たせていた。
レジーは、オスカルが限界近くまで来ていることに気が付いていた。ここでもし優しい言葉の一言でも掛けたら、彼女はもう崩れてしまうだろう。トレーニングを少しでも楽なものに代えたら、彼女はこの試練に負けてしまう。本当に辛いのはあと1〜2日なのだ。ここさえ乗り切れれば彼女は大丈夫だろう。レジーにとっても、愛する者の成長を願って、ここまでの試練を加えるのは本当に辛いことだった。
「今日から、関節技のトレーニングも増えるぞ。技を掛けるとかなり痛いが、容赦はしない、覚悟はいいか?」
「解った。」
「これから俺が教えるのは、いろいろな格闘技をミックスした技だ。その中でも力技ではないものを選んで教える。お前が普通の男相手なら、素手でも闘えるようになってもらう。」
「素手で、男相手に闘うって? 出来るのか、私に。」
「出来るさ、技さえ身につければな。人間の身体にはかなりの急所がある、それを完全に覚えて、そこを一撃で攻められるようにさえなれば簡単だ。急所というのは大体が身体の中心線に沿ってある。一番基本的なところは、男は解るな? ここが一番確実だ。俺もやられたくない。でも、相手も一番弱い所だからガードされ易いので、他の眉間、鼻、顎、鳩尾等も狙い目だ。それを手刀、肘撃ち、膝蹴り等で攻撃する。関節系の締め技もかなり有効だ。後はスピードと連続技で出来るかということだ。細かい急所はまた追々教えていく。取り敢えず、実際にやってみよう。」
「自分の身体で急所とはどれほど痛いのかを感じて貰おうか。大した力で突かなくてもかなり痛いぞ。」
レジーはオスカルを立たすと、次々と技を掛けた。もちろん、オスカルには気づかれないように、かなりの手加減をしていた。
その日は昼までオスカルの悲鳴が響き渡った。関節や急所を攻められるので、傷にはならないが、脂汗が流れるほどの痛みだった。声を出すまいと頑張って見ても、瞬時に技が決まり、攻められる場所があっという間に変わるので、つい悲鳴が洩れるのだった。
午後からはまた剣と銃のトレーニングを夕方までこなし、夕方から夜まではドレスに着替え、所作やダンスの練習。休む時間などまるでなしで、一日が終わる。そして、寝る前は必ずレジーがマッサージにきてくれた。
レジーのマッサージを受けながら、彼女は考えていた。本当にこの場から逃げ出したかった。もう、だめだ。もう、止めさせてくれと言おうと何度思ったことだろう。意地だけで頑張ってきた。また、どうせすぐ朝がくる、どうしてこんなに痛くて、苦しい思いばかりをしなくてはならないのだ。子供のときだって、父に泣き言は言えなかった。姉上たちが母上と暖かい暖炉の前で楽しそうに刺繍をしているときも、私は寒風吹き荒ぶ外でかじかむ手に剣を持たされ、容赦なく厳しい稽古をさせられていた。あの時だって、誰も助けてはくれなかった。自分で耐えるしかないのだと解ってはいる。でも、どうしていつも私だけ? そんな逃げ腰の情けない思いに囚われて、目を閉じたオスカルの脳裏にふと辛そうだった父ジャルジェ将軍の顔が浮かんだ。
(父上がお辛くなかった訳がない、私を愛して下さっていたのだから。私の成長を願い、心を鬼にして私を鍛えてくださったのだ。)
そう気が付いたオスカルが振りかえると、一心に自分を気遣い、少しでも楽になれるように心を込めてマッサージを続けるレジーの真剣な顔が見えた。父上と同じだ。私を本当に大事に思ってくれている人がここにもいる。そうだ、私はまだ頑張れる。大丈夫だ。オスカルは気力が戻ってきたのを感じた。
「レジー、ありがとう・・・」
「「ん? どうした。」
惚けて答えたが、レジーは嬉しかった。彼女の瞳に輝きが戻っている。限界まできていた筈の彼女の精神は己の限界を打ち破ったのだ。もう大丈夫だ、彼女は自分の気持ちを解ってくれた。但し、師としての自分の気持ちだけみたいだけれど・・・。レジーは苦笑するしかなかった。
―つづく―