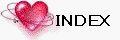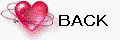オスカルは精神的に落ち着いてきたためか、食欲も戻ってきて、二人きりの食事の時間も楽しめるようになっていた。但し、トレーニング中は禁酒と言われていたので、ワインさえも飲めず、その辺はかなり不満だった。
早朝、二人がランニングで城の外に出ている時間に、近くの村から農家のおばさん二人が、パンと牛乳、野菜、卵、肉、果物、チーズ等の食材を届けてくれることになっていた。そのときにおばさんたちは洗濯、掃除等済ませていってくれる。レジーとオスカルはこの二人と直接顔を合わせたことはなかった。
料理はオスカルが全く出来ないので、レジーが腕を振るった。野菜や肉を適当に切って大鍋に放り込み、ポトフやシチューなどの簡単な煮込み料理を作った。味にこだわる彼の料理だから、もちろん美味い。但し、料理に費やす時間が勿体無いので、1回作ると2〜3日は同じものを食べ続けることになった。
ある朝、いつものようにランニングと柔軟運動を終えて戻ってきた2人は、朝食の準備のために厨房に来た。置かれた卵を見てレジーが、今朝は、ゆで卵が食べたいなと思い、
「オスカル、卵ゆでてくれ。俺は野菜切るから。」と頼んだ。
「え、ゆで卵って、どうやって作るのだ?」
「お前、ゆで卵の作り方も知らないのか? じゃあ、覚えておけ、鍋に卵と卵が被るくらいの水を入れて火に掛ける。それだけ。」
「えっと、鍋に卵と水と・・・。こんなでいいか。で、火に掛けるのだな。よいしょっと。」
「あとは沸騰してから8分待つだけ。時間は俺の好みだけど。」
オスカルは鍋をじっと見つめていた。その間に野菜を洗い、サラダを作っていたレジーにオスカルの実況中継が入る。
「レジー、沸騰したぞ、今から8分だな?」
時計と鍋を交互に見つめる。
「8分経ったぞ。どうするのだ。」
「鍋を火から下ろして、卵を取り出す。やけどするなよ。」
「解った。」
レジーは彼女が真剣に卵に掛かりきりになっている間に、その他の朝食の仕度を全部済ませ、食卓で待っていた。
そこへ得意そうにエッグスタンドに乗せた卵を持って、オスカルが現われた。
「出来たか?」
「うん、簡単だ。」
「これでゆで卵だけは作れるようになった訳だ。」
オスカルはレジーの嫌味も聞こえない風で、スプーンで卵を割ると一口すくって食べた。
「おいしい、こんなにおいしいゆで卵は食べたことがない。自分で作るとおいしいな。」
「はい、はい。良かったな、好きなだけ食べろ。野菜もちゃんと食べろよ。」
久しぶりに見たオスカルの心からの笑顔に、レジーはほっとしていた。
そして、トレーニング開始から、2週間が過ぎようとしていた。
「オスカル、もうその重さには慣れたようだな。」
「ああ、もう大丈夫だ。」
オスカルは腕を上げ、振りまわして見せると得意そうに答えた。
「そうか、今日からもう少し増やすぞ。」
「ええっ・・・。」
「これで終わりだと思ったか? 甘いな。」
オスカルに近づいたレジーの手首をオスカルが瞬時に取ると、締め上げた。だが、返し技で外され、逆に肘関節を取られた。
「つうっ!」
「まだまだ、甘いな。」
そう言ってオスカルの肘を離したレジーの急所をオスカルは膝で蹴り上げた。
「て――っ! これは・・・効・・・い・・・た・・・。」
飛び跳ねているレジー。
「やったー、初めて決まった。」
オスカルはレジーに初めて一矢を報いて得意だった。
「なかなかの上達振りだな。後は投げ技だけだ。筋力も体力もこの2週間でかなり付いてきたし、もう少しだな。じゃあ、追加の鉛板を持ってきてやる。」
レジーはオスカルの前髪を大きな手でくしゃくしゃにすると鼻歌を歌いながら行ってしまった。
夕方になり、いつものようにドレスに着替え、また所作等のレッスンが始まった。
「コルセットもかなり慣れたな?」
「前ほど苦しくはないぞ。」
「最終的にはこのままの姿でも、闘えないと困るのだ。コルセットで締め上げられて、動きにくいドレス姿で闘うのはかなり辛いぞ。」
「まるでやったことがあるような口振りだな。」
「ああ、ある。ちょっと身長が大きすぎるが、座っていればそれほど目立たないし。昔取った杵柄だから、割と女装は得意だ。相手が油断してくれるし。」
「お前の女装か、えらく似合いそうだな。昔はよく女に間違えられていたからな。」
オスカルは、幼年仕官学校時代を思い出してくすくすと笑った。
「さて、今夜はメヌエットか?」
レジーはオスカルの手を取ると優雅に踊り出した。
「奥様、お上手になられましたね。もう、私の足を踏まれる心配はないようですね。」
彼女の耳元でわざとらしく囁いた。
「レジー、うるさい。」
オスカルはレジーの足をわざと踏んだ。
「おっとっと。こちらの方が心配していたのだが、やっぱりちゃんと女だったな。もう問題は何もない。こちらのレッスンは今日で終わりだ。明日からはドレスのままで闘う練習だ。」
「今日で終わり・・・?」
こうして彼の腕の中で踊るのはもうないのかと考え、淋しいような哀しいような不思議な感覚に囚われていた。
「どうした、嬉しくないのか?」
「いや・・・。」
気もそぞろで踊っていたオスカルはつい、ドレスの裾を踏んだ。
「あっ・・・」
オスカルは転びそうになってレジーの腕に縋り、レジーもオスカルをしっかりと支えた。二人は抱き合った格好になってしまい、そのまま呆然と見つめ合った。その刹那二人の胸に衝撃にも似た熱いものが去来した。お互いの心臓の鼓動が耳障りなほど大きく聞こえる。
レジーは彼女の背中に回した手に無意識に力が入り、オスカルは縋りついた手が震えているのを感じていた。
「レジー・・・」
彼を見上げる蒼い瞳が不安そうに揺れていた。
レジーは目を閉じると顔を背け、彼女から手を離して、何事もなかったかのように静かにオスカルに言った。
「今夜はここまでにしよう。」
そしていつものように、ドレスの背とコルセットの紐を緩めると部屋を出ていった。
自分の部屋に戻ったレジーは、どっかと椅子に座り込み、まだ自分の掌に残る彼女の感触に頭を抱えた。
だからいやだったのだ、この仕事を受けるのは。
冗談じゃない、好きな女と二人きりであと2週間だって、有難くて涙が出るぞ。とてもじゃないが理性を保てない。
この2週間だって、俺は自分を誉めてやりたいくらいなのに・・・。
オスカル、あんな瞳で俺を見上げるな。
今はそんな感情に現をぬかしていられないのだ、精神も体力も精一杯の筈だ。今の俺とお前はただの師弟関係だ。そう、ただの・・・。
今夜はもうお前の顔を見たくない、マッサージにも行きたくない。
でも、そういう訳にも行かないか・・・。
酒でも飲みたいが、そんなことをしたら、火に油を注ぐようなものだからな。
ああ、神よ。我に強靭な自制心をお与え下さい。
レジーは覚悟を決めると、いつものように彼女の部屋に向かった。
「オスカル、入るぞ」
いつもなら、ベッドに入っている彼女が今夜は薄絹の夜着のまま窓辺に佇んでいた。月の光を浴び青白く浮かび上がった余りにも儚いその姿に、レジーはしばらく心を奪われ見つめていたが、慌てて目を逸らした。
「どうした、オスカル? 眠くないのか。」
努めて平静を装って彼は尋ねた。
「ああ、何故か今夜は眠くないのだ・・・。身体も慣れてきたのだろうな。」
「そうか、でも、マッサージはしておかないと、明日が辛いぞ。ベッドに横になれ。」
「でも、レジー。お前も疲れている筈だ。毎日私のトレーニングに付き合って、その挙句、食事の仕度とか水汲みとか、雑用も全部お前がやっているのだろう。それなのに私のマッサージまで・・・。今まで気がつかなくて、すまなかった。私も自分のことだけで精一杯だったから・・・。」
「いいのだ、俺は男だし、体力には自信があるからな。」
「レジー、ありがとう・・・。でも、今日のマッサージはいらない。だけど・・・。」
「何だ?」
オスカルは思いつめたような表情で彼に近づくと
「何も言わないで、少しだけこうしていて・・・」
オスカルはレジーの背中に震える腕を回し、自分から抱きついた。
「オスカル・・・」
レジーはかなり驚いたが、黙ってオスカルを自分の胸にそっと抱きしめると、彼女が落ち着くまで、髪や背中をやさしく撫でてやった。
薄い夜着を通して伝わる彼のぬくもり、暖かく大きな彼の掌。撫でられた背中が、髪がとても心地よかった。オスカルは彼の広い胸に顔を伏せて、目を閉じていた。オスカルは自分の心が何かとてつもなく大きなものに包まれて次第に落ち着きを取り戻すのを感じていた。
レジーは腕の中の柔らかな感触と甘い香りに暴走しそうな自分と心の中で必死に戦っていた。でもいくら平静を装って見ても、早鐘のように鳴り響く心臓の鼓動は押さえ込めず、例え言葉を発しなくても彼女に愛していると告げているようだった。
「もう、休んだほうが良い。おやすみ、オスカル。」
彼はオスカルを抱きしめていた腕を離すと彼女に背を向け、そっけない言葉だけを彼女に残し部屋を出ていった。
「おやすみ、レジー・・・」
彼が振りかえってくれることを願いながら、彼女も彼の背に向かって告げた。
一人残されたオスカルは彼のぬくもりの消えてしまった自分を抱きしめて、その場に立ち尽くしていた。
「どうして? 寒いよ・・・、レジー・・・」
レジーは、そのまま城の外へ飛び出した。
このまま到底寝られない。
満月ではなかったが、月の明るさだけで外を歩くのに何の不都合もなかった。
彼はすぐ近くの湖まで行くと、服を脱いで、水に飛び込んだ。春とはいえ、夜のこと、気温もかなり低くなっていたし、水もとても冷たかった。そんな冷たい湖を彼は意味もなく泳ぎ続け、逆上せている身体と心を冷まそうとした。水の冷たさに身体が冷え切っても、彼は月を見上げ、長いこと水に浮かんでいた。
「オスカル、俺のセレネ・・・。」
オスカルは、レジーが戻って来てくれないかと、僅かな期待を胸に開くはずのないドアを見つめていた。
隣の部屋のドアは開かなかった。階段を駆け下りていった音は聞こえた。でも、その後、階段を昇ってくる音は聞こえていない。彼はどこで何をしているのだろう。
オスカルはとても眠れそうもなかったので、バルコニーに出て、月を眺めていた。するとすぐ下の湖で大きな水音が聞こえた。目を凝らして良く見ると、レジーが湖で泳いでいるのが見えた。
残念ながらオスカルには、彼の本当の辛さは解らなかった。
ただ、彼は泳ぎたくて泳いでいる訳ではないということくらいは解った。
二人は同時に考えていた。
仕事だ、これは仕事なのだ。こんな感情はこれからの仕事の邪魔だ。
明日からはきっと何事もなかったように、接してみせる。
そうだ、ただの仕事なのだから・・・。
次の朝――。
どことなくぎこちない雰囲気で二人は顔を合わせたが、お互いに昨夜のことには触れないでおこうと思っていた。
今日からは投げ技のトレーニングに入ると言っていたレジーだったが、顔色が優れないし、どこか元気もなかった。
「今まで、受身と投げられる方はかなりトレーニングした。今度は反対に投げる方だ。いいか、力で投げようとするなよ、投げ技だけだと相手に心得があれば受身を取られてまた反撃を受けてしまう。だから投げ固め技が必要だ。投げてから相手を必ずうつ伏せにして、関節を固める。ここまで出来ないと意味がない。」
レジーはいつものように彼女に何回か技を掛けて見せると、交代して、投げられる方に回った。オスカルは投げるために掴んだ彼の腕が熱いことに気が付いた。
「レジー、お前熱があるのじゃないか?」
レジーの額を触ろうとしたオスカルの手を払いのけると、
「触るな。なんでも、ないのだ。続けろ。」
「でも・・・。」
その日のトレーニング・メニューをなんとかこなし、いつものようにレジーは就寝前のオスカルのマッサージをしていた。
自分に触れる彼の掌はやはり、熱い。
(絶対におかしい、彼はかなりの熱がある。)
「よし、これくらいでいいだろう。早く休めよ。じゃあ、おやすみ。」
レジーはいつものように出ていった。
オスカルは彼が出ていったドアに凭れると、ドアの外の気配に聞き耳を立てていた。隣の部屋のドアが開き、彼は部屋の中に入って行った。そして、ドサッと大きな音が聞こえた。オスカルはやはり彼に何かあったと部屋を飛び出し、隣の部屋のドアをノックしたが、案の定、彼の返答はなかった。思いきってノブを回し部屋に入ると、彼が床に倒れているのが見えた。
「レジー、大丈夫か?」
慌てて駆けよって彼を抱き起こすと、声を掛けた。彼は苦しそうに薄目を開けると
「大丈夫だ・・・」
と弱々しい声で言ったが、彼の身体は火のように熱かったし、彼の意識は既に朦朧としているようだった。本当は朝から熱があったに違いない。でも、彼はおくびにも出さずいつものようにトレーニングに明け暮れたきつい1日を過ごした。
オスカルは彼の腕を取ると自分の首に回し、何とか立ちあがるとレジーを引きずるようにベッドまで運んだ。
彼の息は荒く、顔色は蒼白となっていた。悪寒のため、彼はガタガタと震えていた。オスカルは彼の軍服の上着だけ何とか脱がすと、ベッドに横たえて、上掛けを掛けた。とても寒そうだったので、隣の自分の部屋まで行き、自分のベッドの上掛けも外して、彼の上に掛けてやった。それでも、彼は寒がるばかりで、震えは全然止まらず、うわごとで寒い、寒いと言いつづけた。暖炉を見ると薪は置いてあったので、何とか火を付け、部屋を暖めた。
どんどんと薪をくべても彼の震えは酷くなるばかりで、一向に治まる気配を見せなかった。オスカルは他に彼を暖める方法はないかと考え、不本意ながら以前彼がやってくれたように人肌で暖めることにした。オスカルはベッドに入るとそっと彼の身体を抱きしめた。彼の震えと熱さが伝わってくる。
「熱い・・・。どうしたらいいのだろう。取り敢えず寒気が治まるまでは暖めるしかないな。」
オスカルは自分より彼の方が大きいので、暖めるというよりただくっついているだけのような気もしたが、少しでも彼が暖かくなるように苦心していた。彼も寒さに縋るものが欲しいのか、無意識で腕を伸ばすと目の前にある暖かいもの、即ちオスカルを胸の中にすっぽりと抱え込み少しでも暖まろうとしていた。オスカルは急に抱きしめられてびっくりしたが、彼の好きにさせてやろうとじっとしていた。
しばらくすると熱も上がりきったのか、彼の震えは何とか治まってきた。しかし、熱はかなり高く、意識もはっきりしていなかった。水を欲しがった彼の為にベッドサイドに在った水差しからコップに水を入れて飲ませようとしたが、コップのままではとても飲めそうもなかったので、仕方なく彼の頭を支えて、口移しで飲ませた。
ゴクン――。
日に焼けた彼の喉が上下する。一瞬彼の目が眩しそうに開いたが、何も見えていないかのようにすぐ閉じられた。
取り敢えず彼の悪寒も治まったようだし、後は頭でも冷やしてやろうかと、ベッドを出ようとしたオスカルを彼は意識のないまま、掴んで離さなかった。そして、うわごとで自分の名を呼ぶ彼を放っておけなくてそのまま彼の隣に仕方なく横になっていた。ときどき汗を拭いてやったり、また水を飲ませたりして、苦しそうな彼を黙って見つめていた。
朝方になって彼の熱もかなり下がり、呼吸も落ち着いてきたのを確かめると、安心してしまって、オスカルもそのまま眠ってしまった。
―つづく―