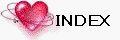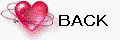オスカルは新たな指令を受け、また一人馬車に揺られていた。とは言え、どこに向かっているのか、相変わらず解らないし、自分のものといえば拳銃が一丁と長剣が一振り。後は今着ている近衛の緋色の軍服と着替えが下着を含め2日分くらいそして、洗面道具だけ。
でも今度は行き先が解っても構わないのか、馬車の窓は開けられていたので、外の景色を楽しむ余裕はあった。目的地まで、かなりの距離があるらしく、途中で食事を取ったり宿屋に泊まったりと時間も掛かった。それでも御者の男は必要最低限の言葉しかオスカルと交わさなかった。
オスカルは馬車に揺られながら、古城から戻ったときのことを思い出していた。
夜半に屋敷へ戻ったオスカルは、父ジャルジェ将軍に挨拶に行った。
娘の帰りを待ちわびていた父はオスカルを一目見るなり、余りの変わりように目を見張った。たった1ヶ月で人間はここまで変われるものだろうか。自分ではそれほどの変化を感じていなかったオスカルは、父の驚きように逆にびっくりしていた。父はオスカルに何も尋ねなかったし、オスカルもまた父に何も言わなかった。ただ、父と娘は黙って目を合わせただけだった。それでも、娘は父の目に安堵を見出し、父は娘の目に自信を見た。
アンドレは、オスカルが出かけて2〜3日後に彼もまたジャルジェ将軍の命令でどこかへ出かけてしまっていて、そのまま帰っていないとのことだった。結局、オスカルは出発までにアンドレに会うことは出来なかった。
途中何度か馬を替え、やっと目的地に到着した。そこは15世紀イギリスとの百年戦争で要塞の拠点となった港町オン・フルールだった。オスカルは馬車を降りると、沖に錨泊されている大きな3本マストの帆船を見据えた。今は帆を下ろしているが、白いセール(帆)を上げて青い空をバックに蒼い海の上を帆走する姿はどれほど美しいだろう。オスカルは元々海と船が好きだったので、逸る心を押さえきれなかった。
彼女は御者に言われるままに艀(*1) に乗り込んだ。
オスカルを乗せた艀は帆船の右舷側に横付けする構えでゆっくりと帆船に近づいた。オスカルは徐々にその大きさを自分の前に見せつける美しい帆船に圧倒されていた。船の甲板でオスカルに向かってにこやかに手を振っている男は、多分最終試験のときに鞭を使ったエミール・マチュー(エミー)だろう。
オスカルはメイン・チェインに捕まり、何とか自力で乗船した。オスカルは大きな帆船に乗るのは初めてだったし、是非一度乗って見たいと思っていたので、辺りを興味深く見まわしていた。
エミーが彼女を呼び、彼の後を付いていった。司令長官室に案内されて中に入るとラップ少将とレジーが待っていて、エミーは中には入らずドアの外で待機していた。
「陸軍近衛連隊長、オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ准将です。ただいま着任致しました。」
敬礼し挨拶する。
「私は海軍歩兵隊々長、アルベール・ガストン・ド・ラップ少将だ。まあ、表向きはだがね。実際のところはフランス諜報部部長で、この船の司令長官(コマンダンテ)でもある。以前から近衛連隊長としての君の評判は聞こえていたし、試験の時の3人からも君の実力の程は聞いている。かなりの腕前だそうだね、期待しているよ。これからよろしく頼む。」
彼は椅子から立ち上がると、彼女に向かって手を差し出し、オスカルと握手を交わした。
自分の前の椅子を彼女に勧め、自分も座りなおした。
「君が女性だということは私と副司令官(セカンド・コマンダンテ)のフォーレ中佐(レジー)しか今のところ知らないが、特に今知らせる必要もないだろう。ご承知のように海の上は純然とした男社会で女性が船に乗るのを嫌う連中も残念ながら多いのだ。詳しい任務については今夜出帆してから説明する。ところで、君のコードネームを決めさせて貰った。『エル・ドール』(黄金の翼)だ。今後は諜報部との連絡は本名ではなく、こちらの名で連絡を取ってくれ。特に君の場合は本名がかなり有名だからね。」
「解りました。」
「君、船は大丈夫かね?」
「解りません。初めて乗ったものですから・・・。」
「そうだな、動いて見なければ解らないか。レジー、彼女に船の中を案内してやってくれ。」
「了解。」
レジーとオスカルは、船の中を歩いていた。
船の名は「ル・ブロンニュー号」。
1758年建造のこの船は東インド会社製作のガレオン船(*2)だった。
目を輝かせて船を見入るオスカルにレジーが先に釘を刺した。
「お前好きそうだが、ロープワークの手伝いするなよ。」
「どうして? 一度やって見たかったのだ。」
「そう言うだろうと思った。だめだ、手が荒れるからな。
今回は貴婦人の役だぞ。手を絶対に荒らすな、ロープなんて触ったらすぐ荒れるからな。」
「手袋をしても駄目か?」
「駄目だ! 手に豆を作った貴婦人がいる訳がないだろう。」
「ちぇっ・・・。じゃあ、マストに登ってもいいか?」
「ワッチ(*3)でも、やる気か?」
「やっていいのか? やるやる。」
冗談で言った言葉に子供みたいに喜んでいるオスカルを見て、レジーは呆れていた。
「お前って男だったら、絶対に海軍向きだな。登りたければボースン(水夫長)に断ってから登れ。それと、帆船で絶対に守って貰いたい事がある。甲板のロープを踏んだり、跨いだり絶対にしないこと。」
「なぜ?」
「帆を止めてあるロープが外れて、帆の力で動くときがある。そんなときに踏んでいたり、跨いだりしているとロープに飛ばされ、海に落ちてあの世行きだ。」
「解った。それとさっきラップ少将が言っていたが、どうして女は駄目なのだ?」
「昔から船は女性だとされていて、船の名前にも女性の名前を付けることが多い。だから女性を乗せると船が嫉妬して、良くないことが起こると言われているのだ。帆船には必ず守り神として舳先にフィギュアヘッドと呼ばれる像が取り付けられる。これも女性を使ったものが多いのだ。」
「ふーん、そうだったのか。」
「だから男だと思われていた方が楽だから、ばれないようにしていろよ。軍服を脱がなければなんとか解らないだろう。」
「解った。」
船尾甲板を通り、一つの船室の前に立つと、レジーはノックをしてドアを開けた。
「ここがお前の部屋になる、相部屋だ。二人で使ってくれ。」
「え? 誰と。」
「残念ながら、俺ではない。彼女だ。」
オスカルの前に腰を屈めてお辞儀をした女性は、燃えるような赤毛をリボンで束ね、優しそうなグレーの瞳をオスカルに向け、にこやかに挨拶した。
「はじめまして、オスカルさま。あなたの侍女を勤めさせて頂きます、シルビィ・コラールと申します。よろしくお願いします。」
侍女としての慎ましやかな衣装に身を包んだ、その女性は明るく利発そうではあったが、お世辞にも美しいとはいえない容姿をしていた。オスカルの乳母のマロン・グラッセを彷彿とさせる体型で、オスカルは却って親しみが沸いていた。
「こちらこそ、よろしく。」そう言って彼女に挨拶したオスカルが不思議そうに振り返りレジーを見た。
「あの、侍女って?」
「ああ、シルビィは元々は私付きの侍女だったのだ、でも今は軍属ではないが、諜報部に属している。彼女は漁師の娘で船に慣れているし、侍女としての仕事振りも大したものだから、ときどき頼むことがあるのだ。お前のドレスの着つけとかも全部彼女に任せておけばいいだろう。」
「シルビィ」
「はい、レジーさま。」
「船の上ではオスカルは男で通す予定だから、そのつもりで。まあ、降りるときには解ってしまうが。」
「解りました。」
「オスカル、間もなく出帆になる。甲板に出て見学してもいいが、一番忙しい時だから、邪魔にならないようにしろよ。それと水夫や海軍の連中と喧嘩するなよ、あいつらもかなり気が短いからな。ごたごたはごめんだぞ。」
「信用ないな。」
「信用出来ないから言っているのだ。俺は出帆準備があるから、行くぞ。船の乗組員については、また後で紹介するよ。」
オスカルは早速出帆の準備が始まっている船尾甲板に出た。この船の副司令官でもあるレジーが、出帆の合図を出す。
「Set all the sails!(*4)(帆走開始)」
船上にレジーの凛とした声が響き渡った。
潮風に彼の蜂蜜色の長い髪が揺れる。紺色の海軍の軍服でその鍛え上げた体躯を包み、操船の指揮を取る彼の姿にオスカルは、いつしか心を奪われていた。
錨が上がり、帆走作業が開始される。
「登れ。」
甲板員が次々とマストに登り、ヤード(*5)を渡ってセールを縛ってあるガスケットを解いて行く。甲板に降りると展帆だ。
「セット・ヘッドスル!」
「セット・ロワー・トップ・スル!」
レジーの号令が次々と伝達され、作業が開始されると甲板上は動索を引く掛け声と号令で騒然となった。帆が次々と開いていく。一枚、また一枚と展帆された帆は風を受けて美しい曲線を描いていく。
オスカルはそんな様子をわくわくしながら、見つめていた。
「邪魔だ、どけ!」
「あっ、すまない。」
素直に謝ったオスカルに水夫長は彼女を一瞥すると
「何だ、お前は。初めて見る顔だが、海軍ではないな。その軍服は近衛の将校様か? 近衛のきれいなお人形さんなら、顔が汚れるといけない。おとなしく船室に引っ込んでいろ。」
「なんだって!」
オスカルは人形という言葉に過剰に反応し、激昂した。
「このやろう、やる気か?」
二人は今にも殴りかかろうとしていた。
「待て!」レジーの声が飛んだ。
「止めるな!」
「今は忙しいから、喧嘩するなら後にしろ。」
オスカルの襟首を掴んでいた水夫長は、しぶしぶ手を離すと
「覚えていろよ。」と捨て台詞を残して、持ち場に戻った。
「お前こそ。」
作業が開始されて約1時間。全部の帆が開かれ横風を受けた本船は、緩やかにヒール(船の傾き)しながら風のみの力で航海を始めた。今日は運良く好天に恵まれ、海は凪いでいたので船が初めてのオスカルには楽な条件だった。
甲板が落ち着きを取り戻したのを見て取ると、オスカルは水夫長に向かって
「さて、さっきの続きだ。」と言い放った。
ひげ面のえらく体格のいい水夫長は大笑いすると
「本気でやるつもりだったのか? おもしろい、でもそんな細い身体のきれいなお人形さんに何が出来るのだ。」
「何でもいいぞ、剣でも、素手でも。」
「おいおい、みんな。この近衛のお兄ちゃんは俺相手に素手で闘うつもりだとさ。」
「おーい、みんな、面白いものが見られるぜ。集まれ!」
水夫や海軍の連中が面白がってぞろぞろと集まってきた。
レジーも黙って見ている。
そんなレジーにエミーが声を掛けた。
「よろしいのですか? ほうっておいて。」
「止めろと言われて止めるようなヤツじゃないし、みんなもあいつのことを解っていた方がいいだろう。」
「そうですね、彼を見た目で判断すると酷い目に合いますから、水夫長も後悔するでしょうね。」
「そういうことだ。見ている必要もないから、俺は先に食事にするぞ。終わったら、あいつも連れて来てくれ。」
「はい、解りました。」
オスカルと水夫長を囲んで、甲板は大賑わいだった。
ラップ少将も噂を聞きつけ、彼女の腕前がどんなものか見てみたくて甲板にきていた。
「素手では余りにかわいそうだ。体格にハンデが在り過ぎるからな。剣にしよう。」
水夫長は剣を抜くと尊大な態度で構えを取った。
「剣でやられたい訳か。」
オスカルは水夫長の隙だらけの構えを見て、少し考えてから剣を左手に持ちなおして構えた。
周りの大きな歓声の中、二人の戦いは始まった。
素早く美しいオスカルの剣さばきに見ていた連中はあっけに取られた。焦りまくって無闇に力で前に出ようとする水夫長に対して、蝶が舞うようにかろやかで無駄のない動きで、水夫長の剣を余裕で受けるオスカル。
「お前、左利きなのか?」
既に息を切らし、顔色を変えながらも、オスカルに尋ねた。
「いいや、左手は今鍛えている最中なのだ。」
涼しい顔で答える。
「ふざけるな。」
その答えにカッときた水夫長は見境なくオスカルに突っ込んだ。レジーとずっとトレーニングを続けてきた彼女にとって、水夫長の動きはまるで止まっているように見えた。彼女は軽く身をかわすと、相手の剣を払い落とし、床に落ちる前に自分の剣でもう一度剣を跳ね上げると、右手で彼の剣を受け止めた。
水夫達のどよめきが聞こえた。
「勝負あったな。」
そう言って2本の剣を収めたオスカルに、水夫長は後ろから殴りかかった。オスカルが彼に殴られたと水夫達が思った瞬間、彼女の身体が沈み込み、彼の身体は見事に甲板に叩きつけられた。彼の身体を瞬時にうつ伏せに返し、肩の関節を固め、締め上げた。一瞬何が起こったのか解らなかった彼も余りの痛みに悲鳴を上げた。
「痛たたた。ま、参った・・・。」
「まだ、やるか?」
「いやあ、止めておくよ。強いのは良く解った、悪かったな。今後は見た目で判断するのは止めておくよ。」
「そうだな、その方が賢明だ。私はオスカル・フランソワだ。船のことは何も知らないから、これからよろしく頼む、水夫長。」
オスカルは彼の腕を離すと立ち上がった。
彼も痺れた腕を擦りながら立ち上がると
「俺は、エドモンだ。気に入ったよ、何か解らないことや困ったことがあれば何でも俺に言ってこい。」
水夫長は、その大きな手でオスカルの背中をバンと叩くと熊のような巨体を揺らして大声で笑った。
この一件で、海軍の連中も水夫達もオスカルに一目置くこととなった。
(これは、すごいな。ここまでとは思っていなかった。
近衛に置いておくのは、勿体無い、ぜひ欲しいな。)
黙って見ていたラップ少将の目が鋭く光った。
―つづく―
艀(*1)
はしけと読みます。渡し舟。大型船と陸との間を往復して、人や荷物を運びます。
ガリオン船(*2)
16〜17世紀にかけて西欧で発達した大型帆船。3本ないし4本のマストと高い船尾甲板を持ち、大洋航海に優れる。軍船、貿易船に用いられました。
ワッチ(*3)
当直。見張りをすること。こういう船の場合は、トップマスト(3本あるマストの一番前のマスト、船によってはフォアマストとも呼ばれる)の上方にある見張台で行われます。映画「タイタニック」でも氷山にぶつかる寸前に出てきました。
Set all the sails!(*4)
船の用語はどの国の船でも、基本的に英語が使われます。
この時代もそうだったと思っていますが、もし違っていたらごめんなさい。
ヤード(*5)
言葉でうまく説明出来ませんので、写真を手に入れました。下記の帆船についての資料をご覧下さい。