オスカルたちの乗った船が転覆する前から、レジーを監視するように見つめる、冷ややかな視線があった。
レジーはオスカルが水面に顔を出したのを確認すると、飛び込もうとしたエミーを制して、自ら湖に飛び込んだ。自分の動きを監視するような視線に気が付いてはいたが、これ以上躊躇しているとシルビィを助けられなくなってしまう。船の係員たちも投げ出された乗客を助けようとしていたが、シルビィの沈んでいく速度が不自然に速すぎ、誰も追いつけないでいた。オスカルもシルビィを助けようと再び潜ろうとしたが、エミーに止められた。
湖底に向かって引きずられるように沈んでいく紺のドレスを追って、必死で潜っていったレジーは、なんとかシルビィを捕まえた。シルビィの右腕にはロープが絡みつき、その先には船の錨が付いていた。その為に異常な速度で沈んだのだった。船から投げ出されたときに運悪くシルビィの腕にロープが絡んだのだろう。ロープを解き、錨を外すとシルビィを抱えて、急いで水面を目指した。レジーとシルビィが水面に顔を出したとき、周りから安堵のどよめきが上がった。
オスカルと他の乗客は既に他の船に助け上げられていた。レジーに向かって近づいた船にシルビィを引っ張り上げてもらい、自分も船に這い上がった。レジーは城に急いで戻るように指示すると、シルビィに声を掛け、頬を叩いたりして反応を見た。何も反応がないと分かると片手を額に当て、もう一方の手で顎先を上げ、気道を確保した。彼女の口元に自分の頬を近づけて、呼吸の有無を確認したが、既に呼吸が止まっていたため、すぐに鼻をつまみ、口から息を吹き込み始めた。城の桟橋に船がついた頃には、シルビィの指がかすかに動き、咳も始まった。そして、大量の水を吐いたのだった。レジーはやっとほっとした表情を浮かべ、彼女の背中をやさしくさすってやった。
「ロッシュ伯爵、こちらの不手際で申し訳ございませんでした。こちらでお運び致します。」
執事が恐縮した面持ちでレジーに声をかけ、城の召使やエミーが代わろうとしたが、レジーは誰にも彼女を渡そうとせずに大事そうに抱きかかえたまま、城内の自分のベッドまで運んだ。
「ロッシュ伯爵、まずは濡れたもののお召し替えをどうぞ。」
レジー自身もずぶ濡れだった。
「いや、私は平気だ。それよりも彼女を。」
「もう大丈夫でございましょう。こちらにお任せください。医者もすぐ参りますので。」
「そうか・・・、ではよろしく頼む。エミー、付いていてやってくれ。」
「はい、お任せください。」
着替え終わったレジーが姿を現すと、医者は、容態は落ち着いているので問題はないし、もう間もなく気が付くだろうと言った。
レジーはシルビィの世話をしてくれていた城の召使と医者に引き取るように言うと、シルビィの枕もとに椅子を運び、座り込んだ。そして、何か紙に書き留めるとエミーに差し出して言った。
「ちょっとこれを、調べてきて欲しい。」
「はい。分かりました。あの、ちょっと伺いたいのですが。」
「なんだ。」
「どうしてあのとき私では駄目だったのですか。」
「いや、本当はお前に任せるべきだったのだ。お前ならあの速度でも潜れた筈だし、間に合っただろう。でも、私が耐えられなかったのだ。監視されていたのは分かっていたのに。こんなことでは、俺もまだまだだめだな。」
「なぜですか。」
「考えてもみろ、こう言っては何だが、ただの召使だとしたら、主人が慌てて助けに行かないだろうな。」
「あっ、そうか。そう言えば、そうですね。」
「そういうことだ。恥ずかしながら、冷静で居られなかった。彼女は俺の妹か、時には姉のような特別の存在だから。」
「そうですか。でも、冷静で居られなかった先輩を、私は尊敬します。」
エミーはにっこりと微笑むとその紙を持って、部屋を出て行った。
入れ替わるように着替えを済ませたオスカルが入ってくると言った。
「レジー、シルビィには私がついているよ。」
オスカルの言葉にレジーは首を振ると
「いや、気が付いたときに俺がいた方が喜ぶだろうから。」
そう言いながら、シルビィの手を優しく握っていた。
「う・・・うん・・・」
微かな声にレジーは慌ててシルビィの顔を覗き込んだ。
「シルビィ。」
シルビィが目をそっと開くと、愛する人のすみれ色の瞳が心配そうに自分を見つめていた。
「あっ、レ・・・だ、旦那様・・・」
「大丈夫だ、誰もいない。レジーでいいよ。」
「レジーさま、私・・・あの・・・ここは?」
「船が転覆したのだ、済まなかったな、お前は泳げないのに辛い思いをさせて。」
「いいえ、そんな・・・。あ、このベッドはレジーさまの。あ、私などが」
そう言って、シルビィは慌ててベッドを降りようと起き上がった。
「シルビィ、そういう言い方をしては駄目だといつも言っているだろう。いいのだ、誰にも文句は言わせない。」
レジーはベッドの端に腰掛けると彼女を労わるようにそっと抱き寄せた。
「お前が無事で本当に良かった。」
「レジーさま。私・・・」
シルビィは突然抱き寄せられて驚いたが、彼の胸に顔を伏せ、しっかりと縋りつくと泣き出した。
オスカルは、その場に居ずらくて、そっと部屋を出て行った。
レジーはシルビィが落ち着くまで、そのまま黙って抱いていた。
「まったく、泣き虫なんだから。」
笑顔でハンカチを差し出した彼に、シルビィは慌てて縋り付いていた腕を放した。
「す、すみません。」
「何か欲しいものは?」
「いいえ、レジーさま、何もありません。ただ、あの・・・。」
「何だ? 何でもいいぞ。」
「ほんの少しの間だけでいいのです、側にいて頂けますか?」
「なんだ、そんなことか。ここにいるから、安心しておやすみ、」
レジーはにっこりと微笑んだ。
シルビィは、嬉しかった。久しぶりに彼と二人きりで居られる。自分を見つめてくれるすみれ色の瞳、そして自分だけに向けられるその優しい笑顔。
シルビィは、ベッドに横になったまま、レジーの顔をじっと見つめ、考えていた。
水の中に引きずり込まれて、もうだめだと思ったとき、力強い腕が私を捕まえてくれた。よく覚えていないけれど、誰かが唇に触れた気がする。懐かしい香りが私を包み、やさしく抱きかかえて運んでくれたような・・・。
まさか、レジーさまが?
そんな訳がないわね。
だって、オスカルさまも同じ船に乗っていらしたのだから。
レジーさまがお助けになるとすれば、オスカルさまに決まっている。
きっと船に乗っていた係員の人か、エミーが助けてくれたに違いないわ。
レジーさまが、私を助けてくださるなんて考えるだけでも、おこがましいわね。
でも、こうして側にいてくださる。
なんて幸せなのでしょう。
あの薬茶の効き目が少しは出ているのかしら?
そうだとしたら、うれしいけれど。
私の願いは叶うことは決してないけれど、少しは夢が見られるかしら。

「あの情報は本当だったわね。まさかあの侍女を助けに飛び込むなんて、信じられなかったわ。これで本当に彼女に利用価値があることが証明された訳ね。」
「はい、奥様。」
「でも、伯爵夫人をなぜ助けに行かなかったのかしら? まさか侍女の方が大事な訳でもないでしょうし・・・。まあその方がこちらとしては都合がいいわ、うまくこのまま手懐けておくのよ。」
「はい、お任せください。手筈は整えてございます。」

「ああ、そうだシルビィ。これを返しておくよ。お前の大事なものだろう。鎖は新しいのに替えておいたから。」
レジーはポケットから例の古びた銀製の十字架を出して、シルビィに渡し、その表情を観察していた。
「レジーさま、これをどこで? どこで落としたのか、分からなくて。ずっと探していたのです。ありがとうございます。」
シルビィは、十字架を手に無邪気に喜んでいた。レジーはその様子に、彼女に何も含むところがないことが分かって安心した。
シルビィが幸せそうな表情で眠ってしまってからも、レジーは彼女の側についていてやった。しばらくして、遠慮がちにドアをノックしてエミーが入ってきた。シルビィを起こさないように、レジーはそっと立ち上がり、彼女から離れたところで小さな声で聞いた。
「どうだった?」
「レジー先輩、船底にやっぱり細工がしてありました。」
「そうか・・・、思ったとおりだな。あの転覆事故はわざと仕組まれたものだったのだな。」
「でも、何のために?」
「詳しくは俺も分からないが、俺がどう動くかを確認したかったみたいだな。俺自身が助けに飛び込んだことが、向こうの希望どおりだったのかどうか分からないが。今回みたいなことがまた起こる可能性もある訳だ。今のところすぐ殺されるようなこともないみたいだが・・・。」
「はい。」
「エミー、ひとつ聞きたいのだが。」
「何でしょう。」
「この間、橋の下で殴られる前に見たものだ。」
「あっ、あの・・・。」
「隠さなくても良い。シルビィを見たのだろう。」
「ご存知だったのですか?」
「ああ、シルビィがその男から何かを受け取っていたのだな?」
「そうです。」
「どうしてあの橋の下へ行ったのだ。」
「実はナンバーワン・ロイヤル・クレッセントに着いたばかりの頃に、他所の侍女からよく当たると評判の占い師の話を聞きました。それでシルビィが一人でその占い師のところへ行ったのです。女性は占いが好きですからね、だから特にそのときは気にしていなかったのですが、それ以来、先輩たちが舞踏会へ行っている間とか、夜中とか度々その占い師の元へ通っていたみたいです。その後の噂ではその占い師がどうも胡散臭いような感じでしたので、一度彼女の後を付けてみようと思っていたのです。あの時も先輩は定時連絡のために出かけることになっていましたし、彼女が一人になればまた何か行動を起こすかも知れないと思って、私は用があって出かけると彼女に告げました。そして、私は出かけたふりをして、彼女が出てくるのを待っていたのです。そして、出てきた彼女をつけて行ったらあの橋へ付いたのです。」
「他には何か見たか?」
「いいえ、それだけです。相手の顔を確認しようとしたら、後ろから殴られて気を失ってしまいました。」
「そうか、分かった。これはオスカルやシルビィには内緒だぞ。」
「はい。」
「明日からそろそろ行動を始めるつもりだから、今夜はもう休んでくれ。」
「分かりました。では、失礼します。」
エミーの後ろ姿を見送ったレジーも、シルビィの穏やかな寝顔を確認すると、静かに寝室を出て行った。そして、隣の部屋で長椅子に座っていたオスカルに向かって言った。
「すまなかったな。」
「ん、何が。」
「いろいろと・・・、」
「謝らなくてはならないようなことは、お前は何もしていないだろう。」
「そうか、ありがとう。」
レジーはすべてを分かって言ってくれているオスカルに感謝していた。
レジーは部屋の窓を開け、夜空に向かい鋭く指笛を吹いた。そしてしばらく何かを探すように夜空を見上げ、左腕を伸ばした。その腕に向かい、真っ直ぐ飛んできた一羽のふくろうがいた。
「レジー、それは何だ?」
オスカルが、後ろから声をかけた。
「俺の大事な仲間だ。伝書鳩のような仕事をして貰っている。鳩は昼間しか飛べない、それだけに鳩では見つかる可能性が高いだろう。ふくろうなら夜目が利くから、安全なのだ。名前は“パック“だ、かわいいだろう。」
「ふふっ、何か面白い顔をしているな。」
オスカルはふくろうの頭をそっと撫でて見た。パックは不思議そうに首をすくめてオスカルを見ていた。レジーは、ふくろうの足に連絡用の管を嵌めると再びふくろうを夜空に放した。
「頼むぞ、パック。気をつけて。」
二人はそのままパックが見えなくなるまで、窓の外を見つめていた。
「今夜は星が綺麗だな・・・。オスカル、"Knight of the
Shining Star(輝く星の騎士)"の話を知っているか?」
「"Knight in Shining Armour(輝く鎧の騎士)"なら知っているが。少女が皆憬れる、いつか自分を迎えに来るという夢の騎士のことだろう?」
「おまえも憬れたのか? 少女の頃に?」
「まさか! 私は自分をほんとうの男だと信じていたんだぞ? 剣の稽古で忙しい最中に、誰がわざわざそんなことを夢見るものか。」
「ふふ、だろうな。」
レジーは複雑な表情をして、黙ってしまった。オスカルは自分が何か悪いことを言ってしまったような気がしたが、それが何故なのかはわからなかった。
気まずい沈黙を持て余していると、ふいにレジーが口を開いた。
「逆の話だよ。少年が夢の少女に憬れるんだ」
そうして彼はきれいな英語で語り出した。
"Long long ago, it's a story of the night..."
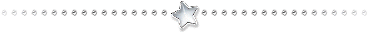
むかしむかし それは星の降る夜の物語
ひとりの少年がおりました
少年には 大切に思っている少女がおりました
星のきれいな晩にだけ現れる 美しい少女でした
ある夜 少年は少女の白い手を握りしめ
頬を真っ赤に染めて
ありったけの勇気をふりしぼって 言いました
きみはあの星のようにきれいだ と
少女は笑って 答えません
そこで 今度はこう言いました
きみと一緒にいると とても幸せなんだ と
少女は ただ黙って 少年を見つめました
吸い込まれそうな 青い青い瞳でした
その瞳に少年は心を決め とうとう告白しました
大きくなったら 僕のお嫁さんになってください
すると 少女の宝石のようにきれいな瞳から
はらはらと 真珠の涙がこぼれおちました
そして 少年の手をふりほどき
青い光に包まれたかと思うと 瞬く間に消えてしまいました
どんなに呼んでも 探しても
少女はどこにもいませんでした
悲しくて 思わず泣き出したくなったそのとき
少年はふと天から降る 優しいまなざしに気づきました
見上げれば そこにはきらきらと青く光る小さな星…
少年は心にちかいます
きみの涙を忘れないよ
僕は 強く 大きくなるよ
あの星に手が届くまで
きみをずっと 見つめているよ
きみこそが僕の 輝ける星
こうして少年は 小さな騎士になりました
むかしむかし それは星の輝く夜の物語
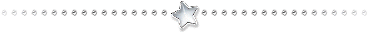
「・・・それでおしまいか?」
オスカルが訊ねる。
「ああ、」とレジー。
「さっぱりわからん、何が言いたいんだその寓話は?」
「・・・わからないか?」
「わかるのか?」
「わかるさ。どうしようもなく男は馬鹿だってことだよ。手が届かないものを追い続ける。いつかはきっと、と夢見て。・・・ま、つまらん話だったな。」
何となく皮肉っぽい声音がオスカルを落ち着かなくさせる。
それが彼女に向けられたものではないとわかっていても。
「いや、別につまらなくはないが・・・」
沈黙が厭で、言葉をつなぐ。
「おまえはその後どうなると思う? いつか青い星は彼の元に戻ってくるんだろうか? それまで彼はただひたすら待ち続けるのか?」
「さあな、」とレジーは気のない返事を返す。
「・・・ま、俺なら夜、海か湖にでも飛び込むかな」
「ええ!? どうして? 絶望して死ぬのか?」
「違うよ、星空の下で泳ぐんだ。彼女が遠くで放つ優しい光に包まれて。」
「・・・・・・」
今度はオスカルが黙ってしまった。
「どうした?」
「女は残酷だな。」
「ええ?」
あっはっは、とレジーは声をあげて笑った。
「何がおかしい、レジー!!」
「はっはっは、おまえが、はは、そんな感想を言い出すとは思わなかったから。」
「だって、それでは少年が救われないではないか・・・。」
「おまえが心配することはないさ。男が勝手に惚れて、勝手に振られて、それでも夢を追い続けているだけなんだ。」
「それで、彼は幸せなのか?」
視線がぶつかり合った。
無言のまま、レジーはオスカルの瞳を見つめた。
そして微笑んだ。
「きっと幸せだよ。」
―つづく―



