シルビィが城の廊下を歩いていると、後から声を掛けられた。
「シルビィさん、私よ。ほら、以前あの占い師のタッソーさまを紹介した、ナンシーよ。」
「ナンシーさんもこちらへいらしていたの? ああ、お会いできて良かった。あの、お願いがあるの。」
「例のお茶が欲しいのね? ね、効くでしょう、絶対に効果があるんだから。この間の船の転覆事件だって、あのお茶のお陰よ。」
「え、何が?」
「あなたのご主人様がご自分の奥様ではなく、侍女のあなたを助けたって、城内の侍女の間で評判になっているのよ。あなたのご主人様って本当にステキよね。あれじゃ、ライバルが多くて大変だわ。」
「え? 伯爵さまが助けて下さったの?」
「知らなかったの? 口移しで息を吹き込んで、誰にもあなたを渡さずにご自分でお部屋までお姫様抱っこで運んで下さったのよ。こう言っちゃなんだけど、ほらあなたってちょっと重そうじゃない。それなのにお姫様抱っこ・・・。いいなあ、あんな見目麗しい良い男に私も抱いて貰いたかったわ。」
(レジーさまが、私を助けて下さったの? オスカルさまではなく、私を? では、あれは夢ではなかったのね。口移しで・・・私のファーストキスはレジーさまと・・・)
シルビィは自分の唇を指で押さえると、頬を染めた。そして、我に返ると慌てて言った。
「ねえ、そのお茶がもう無くなってしまうわ。お願いよ、あのお茶を譲って。」
シルビィは、ナンシーに掴みかからんばかりに懇願した。
「いいわよ。私はもう願いが叶ったから。じゃあ、ちょっとついてきて。」
二人はナンシーの部屋へ向かった。
ナンシーは袋からお茶の包みを取り出すとシルビィに渡した。
「じゃあ、これがお茶ね。それから、これはもっと強い効き目があるのよ。使ってみる?」
ナンシーは小さな紙に包まれた薬のようなものを出した。
「これは何?」
「これをね、ティーポットに入れたお茶の中に好きな人を思いながら1包入れるのよ、お茶だけのときよりも効き目が倍になるのですって。」
「あなたも使ったの?」
「もちろんよ、ばっちりだったわ。もう彼は私にめろめろよ。」
「分かったわ、使ってみる。」
「足りなかったら、また声を掛けてね。がんばるのよ。」
「あなたに教えて貰って、あの橋の下で男の人からたくさん買ったのだけれど、最近彼があのお茶を気に入ってくれたものだから、無くなりそうだったの。どうもありがとう。」
「そんなにすぐ無くなるほど濃く入れているの?」
「ええ、ティーポットにスプーン山盛り2杯と聞いたけれど、4杯入れていたの、いけなかったかしら?」
「大丈夫よ、お茶なんだから。身体にはとても良いお茶だって聞いているし。」
「そうよね、どんどん飲んで貰うわ。」
シルビィはナンシーと別れ、お茶を抱えて嬉しそうに部屋へ向かった。もちろん、ナンシーの目的にはまだ何も気が付いていなかった。『レイヴン』の張り巡らせた蜘蛛の糸に手足を絡めとられ、身動きの出来ない状態にされていることにさえ、彼女は気が付いていなかった。自分の行為が愛する人を窮地に追い込んでいるなどと、考えることも出来ず、ただそこには、恋する女の哀しいまでの願いが、あっただけだった。
レジーは、遅い朝食を済ませると、椅子から立ち上がり、オスカルに腕を差し出して言った。
「さて奥様、城の中の探索でも如何ですか?」
「いいけど、急になんだ。」
「ちょっと調べたいことがあるのだ、一人でうろつくと逆に目立つからな。二人で尤もらしく絵画の鑑賞などして貰いたいな。」
「分かった。で、何を調べる。」
二人は部屋を出ると廊下の突き当たりへ向かって歩いて行った。
「この城は、この間船から見たときに確認したのだが、湖の側から見える窓の数は各階それぞれ15ある。これは1階を別として、それ以外は同じだ。そして、廊下から部屋の数を確認すると片側に5部屋あるのだが、自分たちの部屋でも分かるように一部屋に窓が3つだ。なのに、湖の反対側にある真ん中の部屋だけは少し狭くて、窓が二つなのだ。」
「ということは、窓が一つ合わない。」
「そうだ。一つの窓はただの見せ掛けの窓で、実は窓ではないのだ。そこに部屋は存在しない。だが、何かが存在する。」
二人は問題の廊下の中心付近に来ていた。その左右の壁には共に大きな肖像画が掛かっていた。
「見たところはもちろんただの壁だが、この奥に何かあるとすれば各階が同じ構造だということから、隠し階段だと考えるのが自然だろうな。」
「階段?」
「そうだ、もちろん廊下の反対側にあるあの大階段とは、行き先のまったく違う階段だろう。俺たちには行って欲しくない場所だろうな。」
レジーはそっと左右の壁を叩いて回った。
「やっぱり、こちら側が空洞だな。とすると、この辺に何か仕掛けがある筈なんだが。誰もこないか見ててくれ。」
「分かった。」
レジーは、肖像画に何か仕掛けはないか見た。額縁も絵の裏も丁寧に調べる。次に壁の隅々まで目を凝らし、手で触れて変わったところはないか調べた。
「違うな、どこだ。」
「レジー、誰か来た。」
こちらへ真っ直ぐ向かってくる人間の姿が見えた。
レジーは、オスカルの腰を素早く引き寄せると、その人間に見せ付けるかのように、オスカルに口づけた。オスカルは突然自分に何が起きたのか理解出来ないでいたが、怪しまれない為にレジーがそうしていると気が付いたので、彼の首に腕を回して、素直に彼の口づけを受けた。その人間はレジーたちを見て、大して気にも留めずに近くの部屋に入っていった。オスカルはこれでレジーが自分を離してくれるだろうと思ったが、レジーは尚一層強くオスカルを抱きしめ、狂おしいばかりに深い口づけを繰り返した。口付けは激しさを増すばかりで彼は一向に止める気配はない。オスカルはこれ以上激しい口づけを受けたら、どうかしてしまいそうで、必死にレジーの肩を叩いた。その瞬間レジーは我に返り、弾けるようにオスカルを離すと、冗談めかして言った。
「役得だったんで、つい・・・。」
呆然と立っているオスカルの顔を見ることができずに、レジーはしゃがみ込むと素知らぬ風に足元を調べ始めた。
「ん?」
「どうした、レジー?」
「いや、風を感じた。」
「風?」
「この壁全体が大きく動くみたいだな。ほんの少しだが隙間があるから、空気の流れを感じるのだろう。」
レジーは立ち上がると辺りを見回して、何か仕掛けとなるものはないか探した。そして、廊下の壁に固定されてある燭台に目をつけた。
「よし、これだ。燭台としては不自然な場所に手を触れた跡がある。オスカル壁から少し離れていてくれ。行くぞ。」
レジーは燭台を掴むと下に押し下げた。すると重々しい音と共に壁全体が少し回り、その向こうに現れたのは、やはり階段だった。
「よし、行こうと言いたい所だが、オスカルお前は部屋に戻ってくれ。」
「なぜ、私も行くぞ。」
「その格好でか?」
「あ・・・、でも。」
オスカルはドレス姿だった。
「だめだ、取りあえず様子を見てくるだけだ。深入りはしない、すぐ戻る。」
オスカルはレジーの瞳をじっと見つめると言った。
「分かった、気をつけてくれよ。」
「戻ったら、3人で部屋に何か仕掛けがないか探してみてくれ。これだけの大仕掛けがあるのだ、あの部屋にも何かがあると思う。」
レジーは壁の向こうへ消え、オスカルは急いで部屋に戻った。
オスカルは部屋に戻るとエミーとシルビィに今の経緯を話し、3人で部屋を隈なく捜索した。けれど特に変わったところは見つけられず、徒労に終わっていた。
「オスカルさま、お茶をお持ち致しますね。」
シルビィはそう言って部屋を出て行った。
「そうだな、ちょっと頭を冷やしてから、また考えてみようか。」
そう言いながら、オスカルは暖炉の横にある自分の背丈よりも大きな鏡に近づいた。鏡の周りを縁取っている模様が何となく気になったのだった。
「縁取りに紋章がデザインされているわけか、月に蠍か。たった今見たような気がするのだが、・・・」
「月に蠍の紋章ですか? 確か暖炉の辺りにあったような・・・」
オスカルの疑問にエミーが答えた。
「そうか、暖炉で見たのか、どれだ・・・これだ。」
暖炉の横に置いてある火掻棒の柄に付いていたのだった。オスカルは火掻棒を手にすると、丹念に調べた。鉄製の火掻棒で柄に紋章が彫刻されている、そして先端に凹凸があり、火掻棒としては不思議な形をしていた。
「まるで何かの鍵みたいだな。」
「鍵ですか?」
「そうだ、きっと鍵なのだ。するとどこかに鍵穴がある筈だ。探そう。」
二人で必死に探したが、鍵穴は見つからなかった。
「何か間違っているのかな。火掻棒はここにこんな風にあった訳だ。」
オスカルは元々あった場所に戻して見た。この置き場所は火掻棒を掛けて置くのではなく、金属の筒のようなところへ差すように置いてあったのだった。
「あっ、そうだ。もしかすると。」
オスカルは火掻棒を深く差し込んだまま、時計回りに回して見た。すると横にあった鏡がまるで扉のように音も無く開いたのだった。
「見つけたぞ、ここからどこへ行けるのだろう。」
そのまま入ろうとしたオスカルをエミーが止めた。
「今行ってはいけません。レジー先輩から絶対に勝手に動くなと言われているのです。先輩が戻ってから、指示を仰ぐべきです。」
「そうか、分かった。でも、レジーはどうなっているのだろう。かれこれかなりの時間が経ったのではないか?」
「そうですね。でも先輩ですから、大丈夫です。心配はいりません。ここは元に戻して閉めておいた方がいいですね。」
エミーが鏡に手を置き、閉めようとしたとき、
「ちょっと待ってくれ。」
どこからか、レジーの声がした。
「レジー? どこだ。」
「ここだ、ただいま。エミー、いいぞ戻してくれ。」
レジーは鏡の後ろから現れた。
「なんてところから、現れるのだ。」
オスカルはびっくりして言った。
「いや、俺もここに出られるとは思わなかった。助かったよ、逃げ場が無くなってしまって、どうしようかと思っていたら、暗闇の向こうに急に明かりが漏れてきて、近づいたらお前たちの声だろう。やれやれだ。」
「で、壁の向こう側はどうだったのだ。何があった。」
オスカルが興奮して聞いた。
「まあ、待て。慌てるな。」
レジーが落ち着いた声で言ったとき、シルビィがお茶と共に現れた。
「レジーさま、お戻りでしたか。すぐにレジーさまの分のお茶もご用意致します。」
シルビィは、テーブルにオスカルとエミーの分のコーヒーを置くと、またお茶を入れに出て行った。
シルビィはレジー用のティーポットに、いつもの通り例のお茶をスプーンで山盛り4杯入れると熱湯を注いだ。そして、ポケットからナンシーから貰った紙包みを1包取り出すと包みを開いた。中身は白い粉末だった。その粉末をシルビィは願いを込めてティーポットに入れ、かき混ぜた。
しばらくして彼女が戻りレジーの前にお茶を差し出した。レジーはそのお茶の香りに絶望的な想いに囚われたが、彼女のグレーの瞳を真っ直ぐに見つめた。彼女はそのレジーの視線を真っ直ぐに受け止め、にっこりと微笑んだので、レジーは黙ってそのお茶を口にした。そのお茶は、シルビィの心がこもった哀しい味がした。
そしてレジーは、壁の向こうで見聞きしたことを思い出していた。どこまでを3人に話すべきか、今はまだ3人に全てを話す訳には行かないのだ。
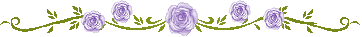
壁を閉めて、隠し階段の2階部分から入ると、階段は、上は城の最上階である4階まであり、下は地下2階まで通じているようだった。2階から4階は客室に使われていることが既に確認できていたので、レジーは真っ直ぐ地下へ向かった。地下は案の定厳重に警戒され、見張りがあちこちに配置されていた。一応今はただ何があるか確認したかっただけだし、それだけの準備も整えてこなかったので、見張りの数や大体の見取り図が書けるように、覚えて行くだけだった。
地下1階は、麻薬工場となっていた。原料となる植物を運び込み、成分を抽出し、精製しているのだった。それにより出来上がっていくのが、例の新種の麻薬『ストーム』だった。レジーは薬学を得意としていないが、この精製方法は驚くほどで、かなりの純度の麻薬を作っていることは確実だった。ということは、この『レイヴン』という組織は、相当の頭脳を持っていることが裏打ちされたということだった。
レジーがここで見たことよりももっとショックだったのは、この地下工場に立ち込める匂いだった。植物を煎じたような、薬臭いような、それでいて今の自分にとってはとても良い香りだと感じられるこの匂い。これは、間違いなく、あの匂い・・・。薄々感づいていたことではあったけれど、それを心の中で認められずにいた。
出来上がった粉末状の『ストーム』を保管してある大きな瓶に近づくと、そっと手を伸ばして蓋を開け、中身を少し取り出すと紙に包みポケットに入れた。
それから、レジーは地下2階へ向かった。
見張りの目を盗み、少しずつ奥へ入っていった。そこは地下牢だった。ひと目でまともな状態ではないと分かる人間たちが居た。『レイヴン』により麻薬漬けにされた美しいお客たちの哀れな末路だった。
結局『レイヴン』は、麻薬及び麻薬常習者を大量に作り、それを外部に排出するのが目的だったのだ。通常の麻薬常習者のイメージを覆す、貴族や金持ちの美男・美女。それらを薬で思うままに操り、イギリスやフランス、はてはヨーロッパ全土にまで、その勢力を伸ばし、金と権力の全てを手に入れる――。
ここが『レイヴン』の本拠地であることはもう間違いないだろう。我々の正体に気がついているはずなのに、なぜ我々をここに招待したのだろう。俺を試すようなことはしているが、特に手を出してくる訳ではない。なぜだ? 何が目的なのだ。
考えながらまた慎重に奥に進んでいたレジーに、牢に一人で入れられている男が目に入った。牢の隅にしゃがみ込んだ男は、髪も髭も伸び放題で、目の焦点も既に合わずに、何かぶつぶつと呟いていた。その言葉にレジーは愕然として、その男を見つめた。
―つづく―
2003/1/3



