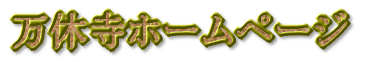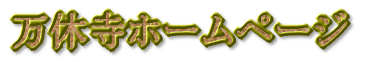|
歎異抄 (全文) 【前序】
竊回愚案、粗勘古今、歎異先師口伝之真信、思
有後学相続之疑惑、幸不依有縁知識者、争得
入易行一門哉。全以自見之覚悟、莫乱他力之
宗旨。仍、故親鸞聖人御物語之趣、所留耳底、
聊注之。偏為散同心行者之不審也云々
【第1章】
一 弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせ
て、往生をばとぐるなりと信じて念仏もうさんとお
もいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨
の利益にあずけしめたまうなり。弥陀の本願に
は老少善悪のひとをえらばれず。ただ信心を要
とすとしるべし。そのゆえは、罪悪深重煩悩熾盛
の衆生をたすけんがための願にてまします。し
かれば本願を信ぜんには、他の善も要にあら
ず、念仏にまさるべき善なきゆえに。悪をもおそ
るべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪な
きがゆえにと云々
【第2章】
一 おのおの十余か国のさかいをこえて、身命
をかえりみずして、たずねきたらしめたまう御ここ
ろざし、ひとえに往生極楽のみちをといきかんが
ためなり。しかるに念仏よりほかに往生のみちを
も存知し、また法文等をもしりたるらんと、こころ
にくくおぼしめしておわしましてはんべらんは、お
おきなるあやまりなり。もししからば、南都北嶺に
も、ゆゆしき学生たちおおく座せられてそうろうな
れば、かのひとにもあいたてまつりて、往生の要
よくよくきかるべきなり。親鸞におきては、ただ念
仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よき
ひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子
細なきなり。念仏は、まことに浄土にうまるるた
ねにてやはんべるらん、また、地獄におつべき業
にてやはんべるらん。総じてもって存知せざるな
り。たとい、法然聖人にすかされまいらせて、念
仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべから
ずそうろう。そのゆえは、自余の行もはげみて、
仏になるべかりける身が、念仏をもうして、地獄
にもおちてそうらわばこそ、すかされたてまつり
て、という後悔もそうらわめ。いずれの行もおよ
びがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞ
かし。弥陀の本願まことにおわしまさば、釈尊の
説教、虚言なるべからず。仏説まことにおわしま
さば、善導の御釈、虚言したまうべからず。善導
の御釈まことならば、法然のおおせそらごとなら
んや。法然のおおせまことならば、親鸞がもうす
むね、またもって、むなしかるべからずそうろう
か。詮ずるところ、愚身の信心におきてはかくの
ごとし。このうえは、念仏をとりて信じたてまつら
んとも、またすてんとも、面々の御はからいなりと
云々
【第3章】
一 善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人を
や。しかるを、世のひとつねにいわく、悪人なお
往生す、いかにいわんや善人をや。この条、一
旦そのいわれあるににたれども、本願他力の意
趣にそむけり。そのゆえは、自力作善のひとは、
ひとえに他力をたのむこころかけたるあいだ、弥
陀の本願にあらず。しかれども、自力のこころを
ひるがえして、他力をたのみたてまつれば、真実
報土の往生をとぐるなり。煩悩具足のわれらは、
いずれの行にても、生死をはなるることあるべか
らざるをあわれみたまいて、願をおこしたまう本
意、悪人成仏のためなれば、他力をたのみたて
まつる悪人、もっとも往生の正因なり。よって善
人だにこそ往生すれ、まして悪人はと、おおせそ
うらいき。
【第4章】
一 慈悲に聖道・浄土のかわりめあり。聖道の慈
悲というは、ものをあわれみ、かなしみ、はぐくむ
なり。しかれども、おもうがごとくたすけとぐるこ
と、きわめてありがたし。浄土の慈悲というは、念
仏して、いそぎ仏になりて、大慈大悲心をもっ
て、おもうがごとく衆生を利益するをいうべきな
り。今生に、いかに、いとおし不便とおもうとも、
存知のごとくたすけがたければ、この慈悲始終な
し。しかれば、念仏もうすのみぞ、すえとおりたる
大慈悲心にてそうろうべきと云々
【第5章】
一 親鸞は父母の孝養のためとて、一辺にても
念仏もうしたること、いまだそうらわず。そのゆえ
は、一切の有情は、みなもって世々生々の父母
兄弟なり。いずれもいずれも、この順次生に仏に
なりて、たすけそうろうべきなり。わがちからにて
はげむ善にてもそうらわばこそ、念仏を回向し
て、父母をもたすけそうらわめ。ただ自力をすて
て、いそぎ浄土のさとりをひらきなば、六道四生
のあいだ、いずれの業苦にしずめりとも、神通方
便をもって、まず有縁を度すべきなりと云々
【第6章】
一 専修念仏のともがらの、わが弟子ひとの弟
子、という相論のそうろうらんこと、もってのほか
の子細なり。親鸞は弟子一人ももたずそうろう。
そのゆえは、わがはからいにて、ひとに念仏をも
うさせそうらわばこそ、弟子にてもそうらわめ。ひ
とえに弥陀の御もよおしにあずかって、念仏もう
しそうろうひとを、わが弟子ともうすこと、きわめ
たる荒涼のことなり。つくべき縁あればともない、
はなるべき縁あれば、はなるることのあるをも、
師をそむきて、ひとにつれて念仏すれば、往生
すべからざるものなりなんどいうこと、不可説な
り。如来よりたまわりたる信心を、わがものがお
に、とりかえさんともうすにや。かえすがえすもあ
るべからざることなり。自然のことわりにあいか
なわば、仏恩をもしり、また師の恩をもしるべきな
りと云々
【第7章】
一 念仏者は、無碍の一道なり。そのいわれい
かんとならば、信心の行者には、天神地祇も敬
伏し、魔界外道も障碍することなし。罪悪も業報
も感ずることあたわず、諸善もおよぶことなきゆ
えに、無碍の一道なりと云々
【第8章】
一 念仏は行者のために、非行非善なり。わが
はからいにて行ずるにあらざれば、非行という。
わがはからいにてつくる善にもあらざれば、非善
という。ひとえに他力にして、自力をはなれたる
ゆえに、行者のためには非行非善なりと云々
【第9章】
一 「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜のこころ
おろそかにそうろうこと、またいそぎ浄土へまいり
たきこころのそうらわぬは、いかにとそうろうべき
ことにてそうろうやらん」と、もうしいれてそうらい
しかば、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房お
なじこころにてありけり。よくよく案じみれば、天
におどり地におどるほどによろこぶべきことを、
よろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもいた
まうべきなり。よろこぶべきこころをおさえて、よろ
こばせざるは、煩悩の所為なり。しかるに仏かね
てしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられた
ることなれば、他力の悲願は、かくのごときのわ
れらがためなりけりとしられて、いよいよたのもし
くおぼゆるなり。また浄土へいそぎまいりたきここ
ろのなくて、いささか所労のこともあれば、死なん
ずるやらんとこころぼそくおぼゆることも、煩悩の
所為なり。久遠劫よりいままで流転せる苦悩の
旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土
はこいしからずそうろうこと、まことに、よくよく煩
悩の興盛にそうろうにこそ。なごりおしくおもえど
も、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるとき
に、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりた
きこころなきものを、ことにあわれみたまうなり。
これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもし
く、往生は決定と存じそうらえ。踊躍歓喜のこころ
もあり、いそぎ浄土へもまいりたくそうらわんに
は、煩悩のなきやらんと、あやしくそうらいなまし」
と云々
【第10章】
一 「念仏には無義をもって義とす。不可称不可
説不可思議のゆえに」とおおせそうらいき。そも
そもかの御在生のむかし、おなじこころざしにし
て、あゆみを遼遠の洛陽にはげまし、信をひとつ
にして心を当来の報土にかけしともがらは、同時
に御意趣をうけたまわりしかども、そのひとびと
にともないて念仏もうさるる老若、そのかずをしら
ずおわしますなかに、上人のおおせにあらざる
異義どもを、近来はおおくおおせられおうてそう
ろうよし、つたえうけたまわる。いわれなき条々
の子細のこと。
【第11章】
一 一文不通のともがらの念仏もうすにおうて、
「なんじは誓願不思議を信じて念仏もうすか、ま
た名号不思議を信ずるか」と、いいおどろかし
て、ふたつの不思議の子細をも分明にいいひら
かずして、ひとのこころをまどわすこと、この条、
かえすがえすもこころをとどめて、おもいわくべき
ことなり。誓願の不思議によりて、たもちやすく、
となえやすき名号を案じいだしたまいて、この名
字をとなえんものを、むかえとらんと、御約束あ
ることなれば、まず弥陀の大悲大願の不思議に
たすけられまいらせて、生死をいずべしと信じ
て、念仏のもうさるるも、如来の御はからいなりと
おもえば、すこしもみずからのはからいまじわら
ざるがゆえに、本願に相応して、実報土に往生
するなり。これは誓願の不思議を、むねと信じた
てまつれば、名号の不思議も具足して、誓願・名
号の不思議ひとつにして、さらにことなることなき
なり。つぎにみずからのはからいをさしはさみ
て、善悪のふたつにつきて、往生のたすけ・さわ
り、二様におもうは、誓願の不思議をばたのまず
して、わがこころに往生の業をはげみて、もうす
ところの念仏をも自行になすなり。このひとは、
名号の不思議をも、また信ぜざるなり。信ぜざれ
ども、辺地懈慢疑城胎宮にも往生して、果遂の
願のゆえに、ついに報土に生ずるは、名号不思
議のちからなり。これすなわち、誓願不思議のゆ
えなれば、ただひとつなるべし。
【第12章】
一 経釈をよみ学せざるともがら、往生不定のよ
しのこと。この条、すこぶる不足言の義といいつ
べし。他力真実のむねをあかせるもろもろの聖
教は、本願を信じ、念仏をもうさば仏になる。そ
のほか、なにの学問かは往生の要なるべきや。
まことに、このことわりにまよえらんひとは、いか
にもいかにも学問して、本願のむねをしるべきな
り。経釈をよみ学すといえども、聖教の本意をこ
ころえざる条、もっとも不便のことなり。一文不通
にして、経釈のゆくじもしらざらんひとの、となえ
やすからんための名号におわしますゆえに、易
行という。学問をむねとするは、聖道門なり、難
行となづく。あやまって、学問して、名聞利養の
おもいに住するひと、順次の往生、いかがあらん
ずらんという証文もそうろうぞかし。当時、専修念
仏のひとと、聖道門のひと、諍論をくわだてて、
わが宗こそすぐれたれ、ひとの宗はおとりなりと
いうほどに、法敵もいできたり。謗法もおこる。こ
れしかしながら、みずから、わが法を破謗するに
あらずや。たとい諸門こぞりて、念仏はかいなき
ひとのためなり、その宗、あさしいやしというと
も、さらにあらそわずして、われらがごとく下根の
凡夫、一文不通のものの、信ずればたすかるよ
し、うけたまわりて信じそうらえば、さらに上根の
ひとのためにはいやしくとも、われらがために
は、最上の法にてまします。たとい自余の教法は
すぐれたりとも、みずからがためには器量およば
ざれば、つとめがたし。われもひとも、生死をは
なれんことこそ、諸仏の御本意にておわしませ
ば、御さまたげあるべからずとて、にくい気せず
は、たれのひとかありて、あたをなすべきや。か
つは、「諍論のところにはもろもろの煩悩おこる、
智者遠離すべき」よしの証文そうろうにこそ。故
聖人のおおせには、「この法をば信ずる衆生も
あり、そしる衆生もあるべしと、仏ときおかせたま
いたることなれば、われはすでに信じたてまつ
る。またひとありてそしるにて、仏説まことなりけ
りとしられそうろう。しかれば往生はいよいよ一定
とおもいたまうべきなり。あやまって、そしるひと
のそうらわざらんにこそ、いかに信ずるひとはあ
れども、そしるひとのなきやらんとも、おぼえそう
らいぬべけれ。かくもうせばとて、かならずひとに
そしられんとにはあらず。仏の、かねて信謗とも
にあるべきむねをしろしめして、ひとのうたがい
をあらせじと、ときおかせたまうことをもうすなり」
とこそそうらいしか。いまの世には学文して、ひと
のそしりをやめ、ひとえに論義問答むねとせんと
かまえられそうろうにや。学問せば、いよいよ如
来の御本意をしり、悲願の広大のむねをも存知
して、いやしからん身にて往生はいかが、なんど
とあやぶまんひとにも、本願には善悪浄穢なき
おもむきをも、とききかせられそうらわばこそ、学
生のかいにてもそうらわめ。たまたま、なにごこ
ろもなく、本願に相応して念仏するひとをも、学文
してこそなんどといいおどさるること、法の魔障な
り、仏の怨敵なり。みずから他力の信心かくるの
みならず、あやまって、他をまよわさんとす。つつ
しんでおそるべし、先師の御こころにそむくこと
を。かねてあわれむべし、弥陀の本願にあらざる
ことをと云々
【第13章】
一 弥陀の本願不思議におわしませばとて、悪
をおそれざるは、また、本願ぼこりとて、往生か
なうべからずということ。この条、本願をうたが
う、善悪の宿業をこころえざるなり。よきこころの
おこるも、宿善のもよおすゆえなり。悪事のおも
われせらるるも、悪業のはからうゆえなり。故聖
人のおおせには、「卯毛羊毛のさきにいるちりば
かりもつくるつみの、宿業にあらずということなし
としるべし」とそうらいき。また、あるとき「唯円房
はわがいうことをば信ずるか」と、おおせのそうら
いしあいだ、「さんぞうろう」と、もうしそうらいしか
ば、「さらば、いわんことたがうまじきか」と、かさ
ねておおせのそうらいしあいだ、つつしんで領状
もうしてそうらいしかば、「たとえば、ひとを千人こ
ろしてんや、しからば往生は一定すべし」と、おお
せそうらいしとき、「おおせにてはそうらえども、
一人もこの身の器量にては、ころしつべしとも、
おぼえずそうろう」と、もうしてそうらいしかば、「さ
てはいかに親鸞がいうことをたがうまじきとはい
うぞ」と。「これにてしるべし。なにごともこころに
まかせたることならば、往生のために千人ころせ
といわんに、すなわちころすべし。しかれども、一
人にてもかないぬべき業縁なきによりて、害せざ
るなり。わがこころのよくて、ころさぬにはあら
ず。また害せじとおもうとも、百人千人をころすこ
ともあるべし」と、おおせのそうらいしは、われら
が、こころのよきをばよしとおもい、あしきことを
ばあしとおもいて、願の不思議にてたすけたまう
ということをしらざることを、おおせのそうらいしな
り。そのかみ邪見におちたるひとあって、悪をつ
くりたるものを、たすけんという願にてましませば
とて、わざとこのみて悪をつくりて、往生の業とす
べきよしをいいて、ようように、あしざまなること
のきこえそうらいしとき、御消息に、「くすりあれば
とて、毒をこのむべからず」と、あそばされてそう
ろうは、かの邪執をやめんがためなり。まったく、
悪は往生のさわりたるべしとにはあらず。「持戒
持律にてのみ本願を信ずべくは、われらいかで
か生死をはなるべきや」と。かかるあさましき身
も、本願にあいたてまつりてこそ、げにほこられ
そうらえ。さればとて、身にそなえざらん悪業は、
よもつくられそうらわじものを。また、「うみかわ
に、あみをひき、つりをして、世をわたるものも、
野やまに、ししをかり、とりをとりて、いのちをつぐ
ともがらも、あきないをもし、田畠をつくりてすぐる
ひとも、ただおなじことなり」と。「さるべき業縁の
もよおせば、いかなるふるまいもすべし」とこそ、
聖人はおおせそうらいしに、当時は後世者ぶりし
てよからんものばかり念仏もうすべきように、あ
るいは道場にはりぶみをして、なむなむのことし
たらんものをば、道場へいるべからず、なんどと
いうこと、ひとえに賢善精進の相をほかにしめし
て、うちには虚仮をいだけるものか。願にほこり
てつくらんつみも、宿業のもよおすゆえなり。され
ばよきことも、あしきことも、業報にさしまかせて、
ひとえに本願をたのみまいらすればこそ、他力に
てはそうらえ。『唯信抄』にも、「弥陀いかばかり
のちからましますとしりてか、罪業の身なれば、
すくわれがたしとおもうべき」とそうろうぞかし。本
願にほこるこころのあらんにつけてこそ、他力を
たのむ信心も決定しぬべきことにてそうらえ。お
およそ、悪業煩悩を断じつくしてのち、本願を信
ぜんのみぞ、願にほこるおもいもなくてよかるべ
きに、煩悩を断じなば、すなわち仏になり、仏の
ためには、五劫思惟の願、その詮なくやましまさ
ん。本願ぼこりといましめらるるひとびとも、煩悩
不浄、具足せられてこそそうろうげなれ。それは
願にほこらるるにあらずや。いかなる悪を、本願
ぼこりという、いかなる悪か、ほこらぬにてそうろ
うべきぞや。かえりて、こころおさなきことか。
【第14章】
一 一念に八十億劫の重罪を滅すと信ずべしと
いうこと。この条は、十悪五逆の罪人、日ごろ念
仏をもうさずして、命終のとき、はじめて善知識
のおしえにて、一念もうせば八十億劫のつみを
滅し、十念もうせば、十八十億劫の重罪を滅して
往生すといえり。これは、十悪五逆の軽重をしら
せんがために、一念十念といえるか、滅罪の利
益なり。いまだわれらが信ずるところにおよば
ず。そのゆえは、弥陀の光明にてらされまいらす
るゆえに、一念発起するとき、金剛の信心をたま
わりぬれば、すでに定聚のくらいにおさめしめた
まいて、命終すれば、もろもろの煩悩悪障を転じ
て、無生忍をさとらしめたまうなり。この悲願まし
まさずは、かかるあさましき罪人、いかでか生死
を解脱すべきとおもいて、一生のあいだもうすと
ころの念仏は、みなことごとく、如来大悲の恩を
報じ徳を謝すとおもうべきなり。念仏もうさんごと
に、つみをほろぼさんと信ぜば、すでに、われと
つみをけして、往生せんとはげむにてこそそうろ
うなれ。もししからば、一生のあいだ、おもいとお
もうこと、みな生死のきずなにあらざることなけれ
ば、いのちつきんまで念仏退転せずして往生す
べし。ただし業報かぎりあることなれば、いかな
る不思議のことにもあい、また病悩苦痛せめて、
正念に住せずしておわらん。念仏もうすことかた
し。そのあいだのつみは、いかがして滅すべき
や。つみきえざれば、往生はかなうべからざる
か。摂取不捨の願をたのみたてまつらば、いか
なる不思議ありて、罪業をおかし、念仏もうさず
しておわるとも、すみやかに往生をとぐべし。ま
た、念仏のもうされんも、ただいまさとりをひらか
んずる期のちかづくにしたがいても、いよいよ弥
陀をたのみ、御恩を報じたてまつるにてこそそう
らわめ。つみを滅せんとおもわんは、自力のここ
ろにして、臨終正念といのるひとの本意なれば、
他力の信心なきにてそうろうなり。
【第15章】
一 煩悩具足の身をもって、すでにさとりをひらく
ということ。この条、もってのほかのことにそうろ
う。即身成仏は真言秘教の本意、三密行業の証
果なり。六根清浄はまた法華一乗の所説、四安
楽の行の感徳なり。これみな難行上根のつと
め、観念成就のさとりなり。来生の開覚は他力浄
土の宗旨、信心決定の道なるがゆえなり。これ
また易行下根のつとめ、不簡善悪の法なり。お
およそ、今生においては、煩悩悪障を断ぜんこ
と、きわめてありがたきあいだ、真言・法華を行
ずる浄侶、なおもて順次生のさとりをいのる。い
かにいわんや、戒行恵解ともになしといえども、
弥陀の願船に乗じて、生死の苦海をわたり、報
土のきしにつきぬるものならば、煩悩の黒雲は
やくはれ、法性の覚月すみやかにあらわれて、
尽十方の無碍の光明に一味にして、一切の衆生
を利益せんときにこそ、さとりにてはそうらえ。こ
の身をもってさとりをひらくとそうろうなるひとは、
釈尊のごとく、種種の応化の身をも現じ、三十二
相・八十随形好をも具足して、説法利益そうろう
にや。これをこそ、今生にさとりをひらく本とはも
うしそうらえ。『和讃』にいわく「金剛堅固の信心
の さだまるときをまちえてぞ 弥陀の心光摂護
して ながく生死をへだてける」(善導讃)とはそう
らえば、信心のさだまるときに、ひとたび摂取して
すてたまわざれば、六道に輪回すべからず。し
かればながく生死をばへだてそうろうぞかし。か
くのごとくしるを、さとるとはいいまぎらかすべき
や。あわれにそうろうをや。「浄土真宗には、今
生に本願を信じて、かの土にしてさとりをばひらく
とならいそうろうぞ」とこそ、故聖人のおおせには
そうらいしか。
【第16章】
一 信心の行者、自然に、はらをもたて、あしざ
まなることをもおかし、同朋同侶にもあいて口論
をもしては、かならず回心すべしということ。この
条、断悪修善のここちか。一向専修のひとにお
いては、回心ということ、ただひとたびあるべし。
その回心は、日ごろ本願他力真宗をしらざるひ
と、弥陀の智慧をたまわりて、日ごろのこころに
ては、往生かなうべからずとおもいて、もとのここ
ろをひきかえて、本願をたのみまいらするをこ
そ、回心とはもうしそうらえ。一切の事に、あした
ゆうべに回心して、往生をとげそうろうべくは、ひ
とのいのちは、いずるいき、いるいきをまたずし
ておわることなれば、回心もせず、柔和忍辱のお
もいにも住せざらんさきにいのちつきなば、摂取
不捨の誓願は、むなしくならせおわしますべきに
や。くちには願力をたのみたてまつるといいて、
こころには、さこそ悪人をたすけんという願、不思
議にましますというとも、さすがよからんものをこ
そ、たすけたまわんずれとおもうほどに、願力を
うたがい、他力をたのみまいらするこころかけ
て、辺地の生をうけんこと、もっともなげきおもい
たまうべきことなり。信心さだまりなば、往生は、
弥陀に、はからわれまいらせてすることなれば、
わがはからいなるべからず。わろからんにつけ
ても、いよいよ願力をあおぎまいらせば、自然の
ことわりにて、柔和忍辱のこころもいでくべし。す
べてよろずのことにつけて、往生には、かしこき
おもいを具せずして、ただほれぼれと弥陀の御
恩の深重なること、つねはおもいいだしまいらす
べし。しかれば念仏ももうされそうろう。これ自然
なり。わがはからわざるを、自然ともうすなり。こ
れすなわち他力にてまします。しかるを、自然と
いうことの別にあるように、われものしりがおに
いうひとそうろうよし、うけたまわる。あさましくそ
うろうなり。
【第17章】
一 辺地の往生をとぐるひと、ついには地獄にお
つべしということ。この条、いずれの証文にみえ
そうろうぞや。学生だつるひとのなかに、いいい
ださるることにてそうろうなるこそ、あさましくそう
らえ。経論聖教をば、いかようにみなされてそう
ろうやらん。信心かけたる行者は、本願をうたが
うによりて、辺地に生じて、うたがいのつみをつ
ぐのいてのち、報土のさとりをひらくとこそ、うけ
たまわりそうらえ。信心の行者すくなきゆえに、
化土におおくすすめいれられそうろうを、ついに
むなしくなるべしとそうろうなるこそ、如来に虚妄
をもうしつけまいらせられそうろうなれ。
【第18章】
一 仏法のかたに、施入物の多少にしたがい
て、大小仏になるべしということ。この条、不可説
なり、不可説なり。比興のことなり。まず仏に大
小の分量をさだめんことあるべからずそうろう
や。かの安養浄土の教主の御身量をとかれてそ
うろうも、それは方便報身のかたちなり。法性の
さとりをひらいて、長短方円のかたちにもあら
ず、青黄赤白黒のいろをもはなれなば、なにをも
ってか大小をさだむべきや。念仏もうすに化仏を
みたてまつるということのそうろうなるこそ、「大
念には大仏をみ、小念には小仏をみる」(大集経
意)といえるが、もしこのことわりなんどにばし、
ひきかけられそうろうやらん。かつはまた檀波羅
蜜の行ともいいつべし。いかにたからものを仏前
にもなげ、師匠にもほどこすとも、信心かけな
ば、その詮なし。一紙半銭も、仏法のかたにいれ
ずとも、他力にこころをなげて信心ふかくは、そ
れこそ願の本意にてそうらわめ。すべて仏法にこ
とをよせて世間の欲心もあるゆえに、同朋をい
いおどさるるにや。
【結語】
右条々はみなもって信心のことなるよりおこりそ
うろうか。故聖人の御ものがたりに、法然聖人の
御とき、御弟子そのかずおおかりけるなかに、お
なじく御信心のひとも、すくなくおわしけるにこ
そ、親鸞、御同朋の御なかにして、御相論のこと
そうらいけり。そのゆえは、「善信が信心も、聖人
の御信心もひとつなり」とおおせのそうらいけれ
ば、勢観房、念仏房なんどもうす御同朋達、もっ
てのほかにあらそいたまいて、「いかでか聖人の
御信心に善信房の信心、ひとつにはあるべき
ぞ」とそうらいければ、「聖人の御智慧才覚ひろく
おわしますに、一ならんともうさばこそ、ひがごと
ならめ。往生の信心においては、まったくことな
ることなし、ただひとつなり」と御返答ありけれど
も、なお、「いかでかその義あらん」という疑難あ
りければ、詮ずるところ聖人の御まえにて、自他
の是非をさだむべきにて、この子細をもうしあげ
ければ、法然聖人のおおせには、「源空が信心
も、如来よりたまわりたる信心なり。善信房の信
心も如来よりたまわらせたまいたる信心なり。さ
れば、ただひとつなり。別の信心にておわしまさ
んひとは、源空がまいらんずる浄土へは、よもま
いらせたまいそうらわじ」とおおせそうらいしか
ば、当時の一向専修のひとびとのなかにも、親
鸞の御信心にひとつならぬ御こともそうろうらん
とおぼえそうろう。いずれもいずれもくりごとにて
そうらえども、かきつけそうろうなり。露命わずか
に枯草の身にかかりてそうろうほどにこそ、あい
ともなわしめたまうひとびとの御不審をもうけたま
わり、聖人のおおせのそうらいしおもむきをも、も
うしきかせまいらせそうらえども、閉眼ののちは、
さこそしどけなきことどもにてそうらわんずらめ
と、なげき存じそうらいて、かくのごとくの義ども、
おおせられあいそうろうひとびとにも、いいまよわ
されなんどせらるることのそうらわんときは、故聖
人の御こころにあいかないて御もちいそうろう御
聖教どもを、よくよく御らんそうろうべし。おおよそ
聖教には、真実権仮ともにあいまじわりそうろう
なり。権をすてて実をとり、仮をさしおきて真をも
ちいるこそ、聖人の御本意にてそうらえ。かまえ
てかまえて聖教をみみだらせたまうまじくそうろ
う。大切の証文ども、少々ぬきいでまいらせそう
ろうて、目やすにして、この書にそえまいらせて
そうろうなり。聖人のつねのおおせには、「弥陀
の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親
鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をも
ちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめし
たちける本願のかたじけなさよ」と御述懐そうら
いしことを、いままた案ずるに、善導の、「自身は
これ現に罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、
つねにしずみ、つねに流転して、出離の縁あるこ
となき身としれ」(散善義)という金言に、すこしも
たがわせおわしまさず。されば、かたじけなく、わ
が御身にひきかけて、われらが、身の罪悪のふ
かきほどをもしらず、如来の御恩のたかきことを
もしらずしてまよえるを、おもいしらせんがために
てそうらいけり。まことに如来の御恩ということを
ばさたなくして、われもひとも、よしあしということ
をのみもうしあえり。聖人のおおせには、「善悪
のふたつ総じてもって存知せざるなり。そのゆえ
は、如来の御こころによしとおぼしめすほどにし
りとおしたらばこそ、よきをしりたるにてもあらめ、
如来のあしとおぼしめすほどにしりとおしたらば
こそ、あしさをしりたるにてもあらめど、煩悩具足
の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みな
もって、そらごとたわごと、まことあることなきに、
ただ念仏のみぞまことにておわします」とこそお
おせはそうらいしか。まことに、われもひともそら
ごとをのみもうしあいそうろうなかに、ひとついた
ましきことのそうろうなり。そのゆえは、念仏もう
すについて、信心のおもむきをも、たがいに問答
し、ひとにもいいきかするとき、ひとのくちをふさ
ぎ、相論をたたかいかたんがために、まったくお
おせにてなきことをも、おおせとのみもうすこと、
あさましく、なげき存じそうろうなり。このむねを、
よくよくおもいとき、こころえらるべきことにそうろ
うなり。これさらにわたくしのことばにあらずとい
えども、経釈のゆくじもしらず、法文の浅深をここ
ろえわけたることもそうらわねば、さだめておかし
きことにてこそそうらわめども、古親鸞のおおせ
ごとそうらいしおもむき、百分が一、かたはしば
かりをも、おもいいでまいらせて、かきつけそうろ
うなり。かなしきかなや、さいわいに念仏しなが
ら、直に報土にうまれずして、辺地にやどをとら
んこと。一室の行者のなかに、信心ことなること
なからんために、なくなくふでをそめてこれをしる
す。なづけて『歎異抄』というべし。外見あるべか
らず。
後鳥羽院御宇、法然聖人他力本願念仏宗を興
行す。于時、興福寺僧侶敵奏之上、御弟子中狼
藉子細あるよし、無実風聞によりて罪科に処せ
らるる人数事。
一 法然聖人並御弟子七人流罪、また御弟子四
人死罪におこなわるるなり。聖人は土佐国番田
という所へ流罪、罪名藤井元彦男云々、生年七
十六歳なり。
親鸞は越後国、罪名藤井善信云々、生年三十
五歳なり。
浄円房備後国、澄西禅光房伯耆国、好覚房伊
豆国、行空法本房佐渡国、幸西成覚房・善恵房
二人、同遠流にさだまる。しかるに無動寺之善題
大僧正、これを申しあずかると云々 遠流之
人々已上八人なりと云々
被行死罪人々。
一番 西意善綽房
二番 性願房
三番 住蓮房
四番 安楽房
二位法印尊長之沙汰也。
親鸞改僧儀賜俗名、仍非僧非俗。然間以禿字
為姓被経奏問畢。彼御申状、于今外記庁納
云々
流罪以後愚禿親鸞令書給也
右斯聖教者、為当流大事聖教也。
於無宿善機、無左右不可許之者也。
釈蓮如御判
|